第1章
あれは暮れのことだった。町内の回覧板が回ってきた。忙しい俺はそんなものはいつでも気にしない。せいぜい息子の散歩のついでにお隣に持っていく程度だ。その分、暇なおゆき婆さんが念入りに読んでくれている。
自室から茶の間に降りてきた時だった。婆さんが、
「ねえねえ若旦那。今度の日曜日、小学校で餅つき大会があるってさ。」
 「へえ、興味ないね。」
「へえ、興味ないね。」ところがその場にいたマリアが、
「餅ツキ見タイ!」
「いやだよ、あんなの。」
「ドシテナノ?」
「だってよ、こないだランニングしてた時、公園で餅つき大会やっててよ、そんとき思ったんだけど、餅つきするときって必ず『大会』って銘打つけど、大規模な会じゃなくちゃ大会とは言わないんじゃないか?」
おゆき婆さんが炬燵の向こうから、
「参加者の少ないマラソンでも、マラソン大会って言うじゃないのさ。」
「そこだよ、それが欺瞞なんだ。近隣住民はできあがった餅の前に行列してたけど、肝心の餅ついてるのは何か専門的な慣れた人だけでよ。あんなのは『餅をふるまう大会』に過ぎないね。」
するとマリアが、
「ソレワ、餅ツキ大会ノ『餅ツキ』ニ対スル批判ニナッテル。ソモソーモ、『大会』ワ何人以上ナラ『大会』デスカ?」
「そうだな…。『党大会』とかを考えたら、百人くらいは集まらないとダメじゃない?」
「♪トモラチひゃくにんできゆかな〜♪」
突然、マリアの膝に坐ってクレヨンでお絵描きしていた元が歌い出した。かわいく思ったので、手を伸ばして、
「お前、歌をいくつも知ってるねー。」
と息子の頭を撫でた。そこへ狐のお紺がやってきて、
「いつも理屈っぽいんだよね若旦ちゃんは。そんなこと言って、餅つきしたいんでしょ本当は。」(12.3)
日本妖怪のお紺は俺の伝統文化好きをよく分かっているが、今回は別だ。公園で見た者どもの民度が低くて幻滅しているんだ。
「しつこいな。あんなのつまらねえよ。」
元「おモチたべたい!」
「お前ね、スパゲッティの絵を描きながら餅食いたいなんて言うなよ。」
元の絵は、画用紙一杯にオレンジ色の線がグルグル散らばっている抽象画だったのだ。ところが、
「スパレッキじゃないもん!」
と元が怒り出した。
「あ、ごめんごめん。じゃあ、それなあに?ラーメン?」
「おとうたんとおかあたん。」
よくよく見ると、無数の曲線の中に人物が隠されているようにも見える。
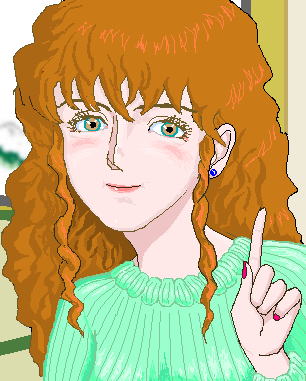 「最近、ハジメワ、オレンジ色ニ凝ッテイマス。子供ヲ理解シナイトネ。オ詫ビノシルシニ、餅ツキ大会。ネ。」
「最近、ハジメワ、オレンジ色ニ凝ッテイマス。子供ヲ理解シナイトネ。オ詫ビノシルシニ、餅ツキ大会。ネ。」と小首をかしげて微笑みかける妻。
「何が《ネ》だ。」と仏頂面しながらも仏心が湧いてくる。「しょうがねえな。おい婆さん、小学校ってどこの?」
「ああ、えーと」回覧板に挟まれた紙をめくり「鷹匠町小だって。10時開催。」
「あそこか。」
「ワカダンチャン出身ノ?」
「いや俺は牛込見附小。鷹匠町ってあれだよ、運動会で岩淵ワニの捕り物が…」
とここまで言いかけて、あの時の可憐な浅野先生のことがありありと脳裏に甦った。(※『決戦!秋の大運動会』参照)もう一度親しくお話ししたいなあ。
「行こう行こう!餅つき大会、是非参りましょう!さあ日曜日楽しみになってきたぞ。朝、ランニングして牛乳飲んでシャワー浴びて、それから…」
俺の変わりように家族一同きょとんとしていた。君子豹変すってやつだ。
続く(2018.10.8)
第2章
早速、鷹匠町小に電話して保護者以外も参加できるのかどうか確認した。せっかく行って閉め出されたらやだもんな。
電話口の女性は、地域に開かれた行事なので大丈夫だと答えた。その声を聴いていて、ふと、あれ?この声、もしかして浅野先生?と直感した。
「あの〜、失礼ですが、あなた浅野先生ですか?」
「え?…私、浅野ですけど、なんで?」
それまで明るく親切そうだった声が少し曇った。でも俺の野性の勘は当たってたぞ。俺は夢中で説明した。
「俺ですよ。緒方ですよ。えーと憶えてねえかな。運動会の時、プールで指名手配犯を逮捕した…。ほら、口髭のさ。それと借り物競走で一緒に走ったじゃないですか。」
相手は思い当たったようだ。「あっ!ああ!」と大きな声を上げた。
「憶えてます。あの、警察と一緒にいた。その節はお世話になりました。」
「あー、いえいえ。懐かしいですね。お元気ですか?」
とひとしきり会話を交わし、餅つき大会でお会いできるのを楽しみにしていますということで電話を切った。
よーし!俄然張り切ってきた!準備万端、抜かりがあってはならない。体力的には日頃走り込んでいるし野菜も運んでるから問題ないはずだが、餅つきというのは、杵の振り方とか臼に手を突っ込むタイミングとか、きっとコツが要りそうだ。練習しとかなしゃ。妻子に恥かかせるわけにはいかない。(そのとき俺の中の良心が「どうせ自分がいいとこ見せたいだけだろ。しかも先生に。」とつぶやいた。)
とはいえ、当店には臼も杵もございません。商店街の知り合いに聞いて回ったが、今どきはどこの家でも餅は買って済ますらしく、誰も持っていなかった。最後に信濃屋の信司の所に回った。蕎麦屋だったらあるんじゃないか。だが残念なことに、倉庫にあった臼は長期間放置されていたため乾燥で割れてしまい、もう使い物にならないというのだ。
「こないだ善ちゃんから、池袋の歳末セールか何かで餅つきやるからって、問い合わせがあってね。引き受けて探してみたけど、この通りだ。」
(※善ちゃんとは善蔵、つまり俺の弟の名。上池袋で島政2号店を経営している。初期作品群参照)
見せてもらったら埃を被った立派な臼が真っ二つ。諦めて島政に戻ってきて、店先の丸椅子にどっこいしょと腰をかけて、腹巻きから煙草とライターを取り出した。やれやれ、くたびれもうけだったぜと煙草に火を点けた。何の気なしに前を向いたら、そこには見慣れた煎餅屋の暖簾が。
「ナヌ?!煎餅屋?」
灯台もと暗しとはこのことだ。煎餅屋にないはずはない。そもそも、まず初めに尋ねるべき相手ではなかったか。俺は向かいに飛び込んだ。
「こんちは〜!餅をつく臼と杵ありませんか?」
「おう!島政さん。」主人が出てきた。「臼と杵って、最近流行ってんのかねえ。」
「え?どうして?」
「もう貸しちまったよ。小学校から頼まれてよ。で、その後だ。おたくの善蔵さんから、何でも池袋で使うからとか何とか…」
くそう小学校め、先を越されたか。いや違うか。小学校で使うってことは俺も参加できるんじゃないか。それはそうと、ないとなれば煎餅屋に用はない。実はこの親父、おしゃべりで有名だから、捕まっては時間の無駄なのだ。
「邪魔したね。じゃあまたな。」
落ち着いて考えよう。近場になくとも、この日本から臼と杵が絶滅するはずはない。かといって全国的に調査するのも現実的ではない。俺が考え込んでいると店番のお紺がお盆でお茶を運んできて、
「どうかしたの?」
「いや別に…。そうだ!お前、杵に化けられない?餅つく杵。」
「あんな単純な物体、朝飯前よ。」
お紺はおやつの後だったせいか上機嫌らしく、すかさすドロロン!店の土間に杵が転がった。
「で、どうすんのさ?」と杵が尋ねる。
「臼はないから本当につく訳じゃねえんだ。実際持った時のバランスを試さないとね。」
と言いながら、柄の部分を両手で掴んで振り上げた。
「きゃっ!ちょ、ちょっと変なとこ握らないでよ!」
杵が身をくねらせた。
「何だ何だ?わからねえよ。第一、その《変なとこ》とやらを持ち手にするなエロ狐!」
暴れると押さえ込みたくなるのが人情というもの。柄をさらに強く握りしごいた。

「イヤッ!離してよもうエッチ!」
杵がグニャリと曲がり俺の額を殴った。
「痛ってー!何しやがんでい!てめえが変態なんじゃねえか!」
どうもうまくいかない。
待てよ、善蔵は結局どうしたんだろう。今頃きっとどこかから調達してるんじゃないだろうかとひらめいた。電話してみたら案の定、他のメンバーがネットで一揃いレンタルしてきて、今度の土日に『池袋商売人祭り冬の陣』で餅つき大会開催の運びとなったと言う。そうか、ネットという手があったか。いやそんなことより、土曜ならリハーサルとして最適じゃないか。兄も手伝うぞとお為ごかしに宣言して電話を切った。
続く(2018.10.8)
第3章
土曜日、池袋に出向いた。10時半頃祭りの会場に着いたが、餅つきはもう始まっていた。弟に頼んで、3番目に蒸かし上がった餅米を搗かせてもらうことにした。
「兄貴、やったことあったっけ?」
「いや、全然ない。」
「大丈夫かよ、昔っからラケットとかバットとか球が当たらなかったじゃねえか。」
「バカ野郎!俺はドラマーだぞ。太鼓には当たるんだから、臼にだって当たるに決まってんだろ。俺のリムショット(※ドラムのヘッドとリムに同時にスティックを当てる技)は百発百中だ。」本当に百発百中なのだ。
「臼の縁に当てたってしょうがねえんだよ。」
「うるさいよ。黙って見てろって。」
蒸し器からもうもうと湯気を立てた餅米入りの木綿布が取り出され、臼へと投入された。さーて、いよいよだぞ。搗く合間に餅を返す相方は弟にお願いした。万が一手が滑ったりしても、身内なら賠償請求されないし。
まずは杵の先っぽで餅米をこねこねして…と。
 「あ〜ら、よっと!」柄を握りしめて振り上げた。「いくぞ!」「おう!」
「あ〜ら、よっと!」柄を握りしめて振り上げた。「いくぞ!」「おう!」「ホイ!」ぺったん「ハイ!」ぺったん、「ホイ!」ぺったん「ハイ!」ぺったん。さすが血を分けた兄弟、息もピッタリだ。「ホイ!」ぺったん「ハイ!」ぺったん。快調快調。俺、筋が良いのかな。「ホイ!」ぺったん「ハイ!」、ぺったん。ところが十回も搗いたらくたびれてきた。杵を高く上げられなくなり、タイミングがずれ始めた。
「うわ!危ねえな!」あやうく弟の手を搗くところだった。
「あ、ごめんごめん。」再び集中。「せえの!ホイ!」ぺったん「ハイ!」ぺったん。
しかし搗けども搗けども、ちゃんとした餅にならない。力の入れ具合が悪いのか、痩せっぽちの俺のパワーが足りないのか?でも明日はこんな醜態を浅野先生に曝すことはできない。何としても今マスターしておかなければならない。
「ハイ!…もうやめといたら?」弟が見かねて、汗の噴き出た俺の顔を下から覗く。
「ひいひい…、いや、途中で投げたら男じゃねえ。俺にはできる!人類はこれまでも多くの危機を乗り越えてきたんだ。ホイ!」ぺったん。
「ハイ!なにを訳の分からないこと言ってんだ?」ぺったん。
でもいよいよ体力の限界が…。背中の筋肉がキリキリ痛み出した。とその時、通りの奥から歓声が聞こえてきた。手を止めてその方向を見ると、人垣の向こうに一際大きいチョンマゲ男。あれは前頭八枚目・高館山だ!隣にいる金髪はイタリア女シモネッタ!俺が媒酌人を務めた若夫婦だ。俺は杵を放り出して駆け寄った。
「おう!どうしたい大将!久しぶり!」
「ご無沙汰しております。さっきお宅へ伺ったら、マリアさんがこっちで餅つき大会だと。で、餅つきと言えば相撲取りの出番。助っ人に来たんでごんす。」
「本当?!助かったぜ。」高館の小山のような肩を叩いて、「ちょうど良かった。ちょっと代わってくれ。もう少しで降参するところだったんだよ。」
善蔵「途中でやめたら同じじゃねえか。」
「やめるんじゃなくてタッチ交代なの!こいつ今《助っ人》って言っただろ。交代は棄権とか負けとかと違うの!プロレスでタッグマッチでタッチしたら負けだって言うのか、お前は?」
「もう、わかったわかった。兄貴の負け惜しみなんかもういいから、高館山さん、一丁お願いしますよ!」
実行委員の弟としても願ったりのはずだ。幕内力士ともなりゃ、有名芸能人みたいなもんだからな。商売人祭り冬の陣もいやが上にも盛り上がるってもんだ。
「負け惜しみとは何だ?今のは負けじゃないという論理の……。まあいいや、頼むぜ高館山関、後は任せた。」
「どすこい!」頼もしげに帯を叩いて片肌を脱いだ。わあっと歓声が上がった。
続く(2020.5.2)
第4章
チリリリリリン!目覚まし時計の音で目が覚めた。アラームを止めようと枕元の時計に手を伸ばしたら、「痛てててっ!」全身が筋肉痛になっていることに気づいた。昨日の餅つきのせいだった。でもこんなことでへこたれてはいられない。今日が本番なのだから。
時間を見ると、もう9時だった。やべえ、昨日セットしたとき時間を間違えたみたいだ。急がなきゃ。隣の妻子の寝床はすでに片づけられていた。もう!起こしてくれりゃ良かったのにと考えながら、ギシギシ痛む身体を起こし、ギクシャクと階下へ降りた。
「おっはよ〜ん!」身体は重いが心は軽い。炬燵でテレビを見ていたおゆき婆さんが振り向いて、
「何が《おっはよ〜ん》だい。いつまでも寝坊して。元ちゃんとマリアちゃんはもう小学校に行っちゃったよ。」
「でもまだ9時だぜ。開会って10時だろ?」
「何か、早く行って校庭で遊ばせるんだって。いつもは小さい子は入れないから。」
「どうして起こしてくんなかったんだよ。」と言いながら、どさっと座布団に坐って煙草に火を点ける。「痛てて…」
「マリアちゃん起こしてたわよ。でも目覚まし鳴っても揺すっても全然起きないから、9時にセットし直して出掛けたのさ。」
いつもは寝覚めは良い方なんだが、昨日の労働が身体によっぽど堪えたようだ。確かにぐっすり寝たなあ。
「だけど、まあ、若旦那あんまり餅つき乗り気じゃなかったから、行かなくてもいいんでしょ。」
「違うだろ!最初はともかくすぐに乗り気になっただろ!だから昨日だって善蔵んとこで練習してきたんじゃねえか!今の俺は餅つき大好きなの!」
「何ムキになってんの?」
「い、いや、別にムキになんかなってない…。あ、きっと腹減ってるからだろ?ちょっとね。」
餅つき大会なんか本当はどっちでもいいのだという本心を見透かされている気がして、慌てて繕った。
「ああ、朝ご飯ね。ちょいとお待ちよ。」
婆さんは立ち上がった。良かった、婆さんは勘づいていないようだ。
煙草を吸い終わってふと茶の間の時計を見たら早くも9時15分。身支度を整える時間を計算するともう時間がない。
「婆さ〜ん、やっぱ飯はいいや!」と立ち上がる。おゆきは台所から、
「何でよ、今お味噌汁温めたのに。目玉焼きだってもう火に掛けちゃったじゃないのさ。」
「しょうがねえ…」坐り直す。たとえ急いでいても、食べ物を無駄にするのはバチが当たる。特に生鮮食品を扱う八百屋を生業としている自分はそう確信する。それに腹減ってると宣言した以上は食べなくちゃ、疑念をもたれる可能性がある。
おゆき婆さんが盆に一汁一菜を載せて運んできた。
「いただきます。」と言うが早いか味噌汁の椀にご飯をぶっ込んで、掻き込んだ。ホカホカご飯に熱々の味噌汁だから結構きつかった。半熟の目玉焼きも麺類の如くツルルッと吸い込んだ。最後にぬか漬けのキュウリを一切れ口に放り込んでお茶をすする。「ごちそうさま。」
「今日はやたら早いじゃない。それじゃ味なんか分からないでしょ。それとも、どうかした?」
「えっ?ど…どうもするわけないだろ。腹減ってたから早かったんだ。ちゃんと美味かったよ。」
おゆきの発言がどうも引っ掛かって困るなあ、と感じながら急いでトイレに向かう。坐りながら今後の効率的な行動の計画を練った。予定していた朝のシャワーは残念だがあきらめよう。でもヒゲは奇麗に揃えなくちゃ。昨夜のうちによそ行きの服を用意しといて正解だったな。いつもの腹巻きじゃ恥ずかしいからな。あっ、パンツのこと忘れてた!えーと、確かまだ買い置きの新品があったはずだ……。ふと、いわゆる勝負パンツみたいなことにまで思いが及んでしまったことに気づいて恥ずかしく思った。《思いの及ばないところを思う》という禅の境地にも通じようか。いや、決してそんなことはない。おっといけねえ、いけねえ。考えすぎて時間をくっちまった。
さあ次は洗面と着替えだ。急ぎでも歯は念入りに磨かないと。そして口髭は短かすぎず長すぎず。髪型どうしようかな。ちょっと寝癖がついてるな。昔みたくオールバックに撫で付けてバッチリ決めようか…。いやいや、ここは自然体が一番だ。小学校の先生にはきっと自然なのが好感度上がるだろう。待てよ、でも意外と野性的な方が…。
首から上がさっぱりしたところで、二階に戻り衣服を着替えた。手早くやろうと努力したが筋肉痛で思うように身体が動かない。普段使わない部位の筋肉痛だからしつこいんだと思う。やれやれ。ちなみに、せっかくだからパンツは新品にしといた。
最後に財布と煙草をポケットに入れて完成だ。あ、眼鏡を拭いてなかった。ハンカチを出してハーッと息を吹きかけて拭き拭き。眼鏡をかけ直し鏡で確認して、よし出来上がり。
するとトイレ第二弾に行きたくなった。いつもは一発で決めてるんだが、これも昨日の疲れからだろうか。それともさっきの朝飯の食い方が胃腸に負担をかけたか?時計をみると、わーっ!もう9時40分じゃん!トイレを端折ろうか、でも学校着いた早々に浅野先生に青ざめた顔で「トイレ貸して」なんてみっともなくて言えない。鬼便じゃあるまいし。それに学校のトイレってウォシュレット付いてないと思うし。やっぱ家で済ませておかなくては。
続く(2020.5.3)
第5章
トイレを出た時は12分前だった。ぎりぎり間に合いそうだ。玄関に走る。靴を履こうとした瞬間、戸がガラガラと開いた。
「若旦ちゃん」雪女ステファニーだ。
「おう、おはよう。」
「今日は珍しいお客様がお越しでござります。誰だと思う?ウフフ」
何だかうきうきしているけど、こっちは付き合ってられないんだけどなあ。
「お客?いや今はちょっと…」

「タラーン!♪」
ステファニーが身体を引くと、その陰に隠れていた人物の姿が現れた。それは後輩雪女のレイチェルだった。(※『IDENTITY CRISIS』参照)
「おー!久しぶりじゃないか!」彼女は相変わらずのウェットスーツだ。レイチェルは、
「Nice to meet you again!」と握手を求めてくる。氷点下のぬくもり。
ステファニー「会津から車ではるばる若旦ちゃんに会いに来て下さったのでござります。今日はゆるりと東京をご案内していただきたく存じまする。」
困るなあ。レイチェルには岩淵ワニのアジト殲滅で世話になったし、もてなしたいのは山々だが、今日は困るんだよなあ。
「あのー、ちょっと今日は急ぎの用事が。」
「でも少しくらい。せっかく来てくれたんだし。」
面倒なことになった。二回目のトイレに行った一手が敗着だったか。あのとき気合いで出発してれば、行き違いでこんなことにはならなかったはず。自らの選択を後悔する。
「東京見物なら俺じゃなくたっていいんじゃない?お前が好きな所連れてけば。」
「それはあまりにあんまりな。暖冬のなか遠路はるばるこうして若旦ちゃんに会いに来てくれて、地元に詳しい若旦ちゃんからいろいろ教えてもらえると思って来たのに。」
申し訳ないがもう時間がない。
「う〜ん、今日は厳しいなあ。えっと、今日は親父の命日で墓参り行こうかなーとか。」
ステファニー「大旦那様はお元気じゃありませんか。」
レイチェルは「Never mind. 私、大丈夫です。」と言って俯く。「アポイントメント取ってこなかった私のミステイク。」
けなげな様子に菩提心が湧いてきた。やっぱ可哀想だな、少しくらい遅刻してもいいか。
「あのさ、どこ行きたいの?皇居とか?」
あそこなら市ヶ谷から目と鼻の先だ。30分くらい適当にあしらって、その足で学校行こう。
ステファニー「いえ、さにあらず。レイチェルは勉強しに上京したのです。」
レイチェル「ヤー。東京のアイスクリーム屋をヴィジットしたいの私。来年の夏、アイスクリームのフードトラック始めようと思って。」
レイチェルがアイスクリームの移動販売車を乗り回していたことを思い出した。
「でも、儲けるにはグッドセラーズ(売れ筋)のアイテムがなくちゃ。東京なら、冬でもいろんな場所でアイス売ってるでしょ。インスタ映えするオリジナルのアイスを研究したいの。」
なるほど、見上げた心がけだ。起業家精神は感心感心。でも俺には使命が!
「立派だと思うけど、俺アイスのことなんか詳しくないから。」
「でも土地勘はあるではありませぬか。道案内は若旦ちゃんが最適にて。」
「それに最近じゃフルーツだけじゃなくハーブなどを練り込んだアイスもいっぱい出てきてるの。私、専門家のオピニオン聞きたい。」
「でもなあ……、ごめん!どうしても外せない先約があるんだ。」
と目をつむって手を合わせたら、そこへおゆきが出てきて、
「薄情だね若旦那、見損なったよ。こんなに頼りにされてんのに。ちょいとばかし可愛い先生がいるからってさ。」
ゲゲーッ!見破られてたかっ!咄嗟に俺は白ばっくれなければならなかったが、狼狽は隠せなかった。
「ななななな、何を?いったい何のこと言ってんのババア、いいいいい加減なこと抜かさないようにしましょう!」
婆さん、得意満面の表情で、
「妻子の目は欺けても、このおゆき姐さんの目はお見通しさね。ちゃーんとネタぁ上がってんだ。」
赤ん坊の時から世話になってんだからそうかも知れない。でもそんな賢人じゃないことは俺が知ってる。
「ネタもクソもねえ!だいたい俺はだな、行きたくもなかったけど元とマリアがだな、餅つき見たいって言ったから……、それで何だっけ、スパゲッティを元が描いてたのを間違えたのは俺が悪かったが…。」まだ心の動揺が。
「観念おし。今から順序立てて教えてやるから。」
芸者探偵おゆきかよ。承ろうじゃねえか。ここは一旦相手に手を預け、落ち着きを取り戻すんだ。
「一昨日、お線香買いに仏壇屋さん行ったらさ、ちょいと話し込んじまってさ。」
「ああ、あの爺さん婆さんで細々とやってる。で?」
「でさ、そんとき聞いたのよ。今年はなぜか鷹匠町小の餅つき大会に問い合わせが殺到してんだって。それが、今年の新任に美人の女先生が入ったからだってんだよ。この辺の男どもが行きたがってるらしいのよ。」
恐るべし、高齢者のネットワーク。でもどうせ井戸端会議の噂話だろう。
「バカ言え。そんなの根も葉もない噂じゃねえか。だって、どうして問い合わせが町内の奴等だと……」
その時ハッとした。あの回覧板だ!
「フフフフ…。ようやく判ったようだね?例えば、信濃屋の信ちゃんだろ?豆腐屋の次男坊だろ?松芝電気の梅さんだろ?近江屋さんは80歳だからシロだね、アハハハ。」
なんと!商店街の野郎どもめ、どスケベ親父だ。しかしながら、あっぱれな審美眼だ。みんな男だ!男たる者、上玉は見逃さない。ところがどっこい、俺様は浅野先生と借り物競走で手をつないでゴールインしたという物理的接触を果たしておるのだよ。アドバンテージなのですよ。ヘゲモニーなのですよ。
いかんいかん、今はその辺の優越感は抑えて、真実を追及し冤罪を晴らさなくては。
「けどどうしてそんな個人が特定できんだよ?所詮てめえの当て推量だろ?何だよ近江屋は80だからシロだって。失礼だぞ。」
「あたしゃそこらは抜かりないわよ。お紺ちゃんがヒマそうにしてたから、聞き込みしてもらって裏ぁ取ったのさ。」
「お紺?」
「ほら、お紺ちゃんって、中身のお転婆はともかく、娘の姿でいたらパッと見、ミステリアスじゃない?エクトプラズムってのかしら。目なんか黄色くてさ。」
「えっと、それはエキゾチックとか言いたいのか?まあまあ、見方によっちゃな。そもそもが妖怪変化で、しかも畜生だからな。」
だから日本人離れっていうより人間離れというのが正確だが。
「だからさ、あの子がニッコリ笑って猫なで声出すと、大抵の男どもはつい鼻の下伸ばしてころころ本音を吐いちまうのよ。」
言われてみれば、あの狐のチープな色香で高館山の親方もメロメロだったっけ。(※『帝城ブギウギ』参照)
「でさ、本人たちの口から、学校の先生が可愛いから餅つき大会行くんだって聞いてきたんだよ。てことは、大方あんたも同じ穴のムジナだろうよ。」
くそー、ここまで外堀を埋められては……。でも待てよ。俺はお紺に自白した憶えはない。まだ土俵際で踏ん張れそうだ。
「ほほう、よく調べたじゃねえか。けど、この俺がその先生に会いたがってるって証拠がどこにあるんだい?」
と、そこへ突然お紺が天井裏から逆さまに顔を出した。
「だってこないだ電話してたじゃない。《楽しみにしてます》とか言ってさあ。」
あっちゃー!そうだった。あれを聞かれてたのか。盗み聞きしやがってこの女狐め。
「この性悪狐、盗聴は憲法違反だぞ!通信の秘密ってのを知らねえか!基本的人権だ!」
「どうせあたい畜生だし。♪人間なんてララーラララララーラー♪人権なんてララーラララララーラー♪」(5.3)
「こん畜生め…。あのなあ、人間様の世界じゃ《楽しみにしてます》なんて普通の社交辞令なの。今度行きますからよろしくどうぞって程度の挨拶だろ。バカじゃねえか?俺は先生なんかに興味ないの!」
お紺はにやにやして、
「へえ、そう。何か嬉しそうだったけど。へへへ、名前までチェックしちゃってさ。確か名前があさ…」
「ワワワワワーッ!」と叫んで両手で逆さ吊りになっているお紺の口を塞ぎ、そのまま首っ玉掴んで天井から引きずり降ろした。これ以上の恥辱には耐えられなかった。お紺は勢いよく地べたに落下した。お紺は尻餅ついた状態で、


「痛ったーい!女の子に暴力振るうなんて最低!」
「どこが女の子だ。てめえ何百年生きてんだよ。」
それまで黙って見ていたステファニーが、「若旦ちゃん、もしかして浮気?」と言い出した。眼の奥に怒りの炎が灯っている。こいつは俺にほのかな恋心を抱いているんだ。
「絶対そうじゃない!浮気なんて全っ然!」
「されど今までの話から察すれば…」
長く仕えてくれているこの雪女の純情を踏みにじることはできない。
「うーん、じゃあこの際だから正直に言うけど、そりゃあ運動会のとき好印象は持ったけど、それ以上でも以下でもない。全然そんなんじゃない。」
「そんなんじゃなければどんなのよ、好意持ったってことでしょ?」
「だからその……そうだ!プラトニックラブだ。」得意の理屈がひらめいた。「わかるか無知なる妖怪どもよ。イデアだよ。イデアを思慕する愛だよ。知への愛、フィロソフィア。」
ここでまたお紺が口を挟んだ。「ふーん、あたい無知だから知らないけどさあ、プラトニックラブな人がわざわざ新品の勝負パン…」
「ワワワアアア!」再びお紺に掴みかかった。この変態狐め、俺の着替えまで覗いてやがったのか。今度はお紺はひらりと身をかわし、ジャンプ一番、天井裏へ飛び込んだ。
「ここまでおーいで!あっかんべー!キャハハハハ!」
「だっ、だからあれは、見えない所にこそ身だしなみだ。武士は戦いに臨んでまっさらなフンドシを…」
「ほーら、別の一戦を期待してたんじゃないの?」
「口の減らねえけだものめ。ホントだよ武士のたしなみは。ふん!これだから教養のない動物とはお話になんないね。」
「あっそう。教養ぶるんだったら、せめて《秘すれば花》くらいのことは言ってもらいたいわよね。無知なるけだものからのアドバイス。」
「うっ…。やな奴だなあ〜。」教養面で意表をつかれてしまい、二の句も継げなくなった。
おゆき婆さんがたしなめるように、「もういいだろ?お前さんに勝ち目はないよ。」
腕時計を見たらもうとっくに10時を過ぎていた。参りました。無条件降伏です。もうどこへでも参ります。何でも言うこと聞くから、マリアにだけは内緒にしてほしいなあ。
読者諸氏は俺が簡単に諦めたことに疑問を持つかも知れない。和辻哲郎が『風土』で、日本の国民的性格を「しめやかな激情、戦闘的な恬淡」って表現している。俺は、パッとあでやかに咲きパッと潔く散る桜花を好む日本的心性の持ち主なのだ。要するに、あっさりしていて未練たらしくないのだ。
それにしても悔しいなあ。今ごろ町内のヒヒ爺ぃどもは浅野先生囲んで楽しく飲み食いしてるんだろうなあ。俺のアドバンテージも解消か。(我ながらどこもあっさりしていない。)
結局その日は、レイチェルの運転するアイスクリームカーでネット情報を頼りに23区内をぐるぐる回り、一日中アイスのリサーチをした。夕方、鷹匠町小の前を通ったが、校庭も校舎も夕陽を浴びて静かに佇み、餅つき大会は跡形もなく消えていた。
完(2020.5.4)
