モンゴルから帰国し、ひとっ風呂浴びて晩酌しつつ俺が家族を相手に土産話をしていたら、
「へえーっ?!狼男に会ったの!」
と、横でいなり寿司を頬張っていた狐娘のお紺がびっくりした。
「そうなんだよ。すげえだろ。」
「あたいも会いたかったわあ。それで?それで?」
積極的なあいの手というものは話し手にとっては嬉しいもんで、話にノリが出てくることは皆さんもご経験があると存じます。お紺の方に身を乗り出し、
「それがさ、鬼便の野郎がさ、あいつはがっついてるからさ…」
と言いかけたら、マリアが、
「狼男?ソレワ“
「でもモンゴルだって狼は普通にいるぜ。」
「デモデーモ、日本ワ狐トカ狸ガオ化ケ、コレワ当然、ヨクワカル。ソシタラ逆ニ、狼ワヤパリ、エウローパノ深イ森ノ生キ物ト思ウノ。羊ヤ赤ズキンチャントカノ関係デス。」
「アジアには狼男がいないってのか?」
「文化ヨ文化。例エバ、オ岩サントゾンビノ違イ。ッテ言ウカ、河童ト、マーメイド?」
マリアも雪女や化け狐と暮らすようになって、その辺の教養は十分深まっているようだ。それに対し、傍らでアイスクリームをなめていたステファニーが、
「されど、古来日本にても、取り憑かれた家には『狐憑き』と似た意味で『犬神憑き』とか呼ばれた家もござりました。さような家は村の中でなかなかに存続致しかねたやうで…」
「フ〜ン」
さすがに500年間存在している雪女の話、マリアも素直に聞いている。
あ、そうか、妖怪どもなら100年以上前に絶滅した日本狼とも面識があるかも知れない。
「そういえばお前ら、狼って見たことある?」(11.7)
雪女、小首をかしげながら、
「ええ、私も山間部が職場ですから見かけたことはござりますが、奴等は集団活動主体で、閉鎖的なコミュニティを作って居りますれば、知り合うことは叶わぬままなりけり。」
お紺も同調し、
「あたいも。あいつら、なかなか堅物みたいだったよね。」
俺「ふーん、俺なんかモンゴルの狼と交信できたけどなぁ。それで友達になったよ。」
すると二人が急に、
「えーっ?!若旦ちゃん、テレパシーできるの?!」
と大声で言うもんだから、俺は気後れした。
「あ…いや…。まあ、a littleって程度かな。」
お紺が山吹色の瞳を輝かせ、「ねえねえ、やってみせてよ。」
雪女が「是非に!」
マリアも「ゼヒ、私ニモ下サイ!是非ノ心ワ智ノ端ナリ。」
(※最近マリアはなぜか『孟子』を読んでいる。)
モンゴルの時は緊急事態だったから、臨時で超越的な能力が出たような気もしている。今できるとも思えない。
(※とはいえ、俺も人間だから超越論的主観性は持ち合わせている。でもこれは要するにカントが言い始めた科学の客観的確実性を担保する理性的能力であって、テレパシーとは無関係だ。テレパシーなんて、カントに言わせりゃ純粋理性のアンチノミーってとこだろう。)
でも一度はできたんだから試してみる価値はある。
「それじゃあやってみるか。」
俺の一声で、一同正座になった。すると、いち早く夕飯を済ませ、居間の隅で元とパズル遊びをしていたおゆき婆さんが、
「さあ、元ちゃん。あんたのお父ちゃんがテレパシー出すんだってよ。」
と言って元の脇を抱え上げ、膝の上に乗せた。実験に参加するつもりらしい。元は俺の方を向いて、
「テデパシーってなあに?」
「え?…えーと、んーと、言わなくても解るってことだな。」
だが息子は「?」という顔をしている。困ったぞ。幼児に分かる表現じゃなきゃ。
「あのね、ビビビビーッと目に見えない光線が出るんだ。」
これを聞いた途端、元は立ち上がり、
「シュワッチ!シュペシュームこうせん!ヘアッ!」
と叫んで手を十字に交差させて俺に向けた。俺は反射的にやられなければならない。
「ギャオーー!!グオーッ!」
仰け反って畳に倒れ込む。少しヒクヒク痙攣してからばったりと動きを止める。元は腰に手を当てて俺の最期を見届けると、
「ピコンピコンピコン」
とカラータイマーを口で唱えながら空を見上げ、
「シューワッチャ!」
両手を掲げて飛び立っていった。俺の情操教育は着実に息子の魂に根付いている。
ところが実は、ウユトヤマンを飛ばすのも俺の役目だ。寝っ転がった状態で、元を巴投げのような感じで足の裏に腹を乗っけて持ち上げて飛ばしてあげるのだ。ここまでやらなきゃ正義の味方は納得しないのである。自分の教育にも矛盾を感じる。
満足した元は、マリアに連れられてお風呂に向かった。(11.8)
「やれやれ。で、何の話だったっけ?」
「だからテレパシー!」
「あ!そうそう。では、改めて…」
何を送ろうかな。膳の上のハムサラダが目にとまった。そうだ。ボンレスハムの画像を送ろう。なるべく単純な形の方が分かってもらいやすいはずだ。
瞼を閉じて、脳裏には紐でくくられたご贈答用のボンレスハムのイデアを思い浮かべ、眉間にエネルギーを集中する。30秒ほどした頃いきなり、
 「若旦ちゃんのエッチ!痴漢!」
「若旦ちゃんのエッチ!痴漢!」「変態じゃないの?!」
と、二人の妖怪に頭をひっぱたかれた。
「何しやがんでい!」
お紺、「だって今、SMプレイのシーンが来た。」
「え?何それ?」
「なんかグラマーな女の子を若旦ちゃんが縛り上げているの。」
「あれ?そんなの送ってないぞ。ハムの塊を思っただけなんだけど。」
雪女、「本当?」
「当たり前じゃんか!誰が好きこのんで自分の変態を自分から暴露するんだよ!」
どうやら、信号がおかしく変換されてしまったらしい。
「じゃあ本音のところではやっぱり若旦ちゃんはドSだったの?」
「違う違う!そんなこと、一つも考えなかった。私は誓います。そして私の性癖はノーマルです。」
お紺が疑いの眼差しで、「どうだか。」
「何だよその目は。俺が変態だったら、お前らだって今頃無事じゃないぞ。そうだろ。これまで指一本お前らに触れてないだろ。」
「まあ、そうね。」
誤解は解けたが、テレパシー実験は失敗に終わった。
続く(2016.12.4)
第二章
翌日、俺は鬼便を見舞った。前話で馬に引きずられてボロボロになった傷はまだ癒えていない。鬼便は自宅療養中であった。
「海外旅行保険に入っていたから、ウランバートルの時の治療費は保障されたんだけど、」
「ふむふむ。」
「でもどうも最近毛深くなってきたみたいなのだ。モンゴルでホルモン注射でもされたんじゃないかな。医療ミスだったら、どうやって賠償させればいいのか。」
「でも鬼便、前から胸毛とかあったじゃねえか。ヒゲだってもともと濃いしよ。」
 「でも、こんななんだ。」
「でも、こんななんだ。」と言いながら、パジャマの前ボタンを外し胸元を広げた。見れば胸から腹にかけてモジャモジャだ。キッスというかフレディーというか、真っ黒けの毛。
「いいじゃねえか、男らしくて。俺から見りゃ羨ましいよ。」
「そんなのは本人じゃないから言えるんだ。チルコ殿は毛深いの嫌いなのだ。」
「じゃあ剃れば。」
「無論。いっそ永久脱毛しようかな。」
「いや〜、エステはあんたにゃ似合わないだろ。それにエステって旅行保険利くの?」
「あーそうか。自腹じゃやめとこうかな。」
相変わらずケチくさい奴だ。
* * * * * * * * * *
その夜のことだった。狼の夢を見た。俺は夜の草原に立っている。狼が遠くからやって来て、俺にテレパシーで、
「鬼便に取り憑いて日本に帰ってきたが、あいつはアレルギー薬だの喘息薬だの睡眠導入剤だの抗うつ剤だの薬漬けで、とてもじゃないがあの肉体には長居できない。新たな依り代におぬしの身体を借りるぞ。」
と伝えられた。目覚めると寝汗でびっしょりだった。嫌な夢を見たなぁ。鬼便が毛深くなったなんて言うから、狼男の記憶と繋がっちゃったんだろう。風に当たりたくなって寝室の窓を開けると弦月が輝いていた。
ところがそれはただの夢ではなかった。次の日、出勤しようと通りに出たら辻川の婆さんが飼い犬の秋田犬のマルを連れて散歩していた。いつもは尻尾振って俺に寄ってくるマルに吠えられた。おとなしいマルが吠えるなんて、俺が子供の頃、マルの鼻の穴に指を突っ込んだとき以来だ。たまたまマルの機嫌が悪かったのか、俺に何かマルの嫌う要素があったのか分からなかった。
原因が判明したのは、市場に仕入れに行っていたお紺が店に戻ってきた時だった。軽トラックの助手席から降りてきたお紺は俺の顔を見るなり、四つん這いになって、
 「ウーッ!」
「ウーッ!」と唸り声をあげて、睨みつけてきた。突然のことで困惑し、後ずさりした。
「な、何だ何だ?」
するとお紺は、
「魔物め!退治してやる!」
と言うが早いか、ジャンプ一番、俺に跳びかかってきた。防御態勢をとる間もなく、お紺の犬歯が俺の左の肩に突き刺さり、勢い余って両者は地べたに倒れ込んだ。
「痛てててて!!」
側にいたステファニーと俺の親父が慌ててお紺を取り押さえ、俺から引き離してくれた。座り込んだ状態で血のにじむ肩を押さえながら、
「とち狂ったか、化け狐!」
と親父に羽交い締めにされているお紺に向かって言い放つ。お紺は雪女に、
「ステファニー、あいつ魔物だよ。若旦ちゃんの姿に化けてるけど。」
「えっ?」
ステファニーは振り向いて俺をじっと見つめた。
「お、お、俺だよ俺。いつもと変わらない若旦ちゃんだよ!ほらほら。」
思わず両手を広げてみせた。俺は正真正銘の俺だと。武器も何も持っていないぞと。肩の咬み傷が痛んだ。雪女は用心深くそろりそろりと俺の10cmくらいの至近距離まで来て、顔、首、頭などを前後左右から舐めるように観察して、匂いをクンクン嗅いだりして、
「ははあ、分かった。お紺ちゃん、これは魔物が化けておるにあらざらむ。若旦ちゃんは取り憑かれておるご様子。」
聞いたお紺は合点したようで、攻撃の気色は消え、
「ああ、そうかも。」
あれは正夢だったのだ。日本狼の魂は、鬼便の不健康・不健全な身体から俺に乗り換えたのだ。あんな奴のところに見舞いに行くんじゃなかった。
続く(2016.12.4)
第三章
鬼便に電話したら、今朝になったら毛深い体毛がウソのように消えてしまっていたという。間違いなさそうだ。
それにしても不思議なのが、取り憑かれているにしては人格に変化がないことだ。普通(と言えるかどうかがそもそも分からないが)、物の怪に取り憑かれるというのは精神がまず乗っ取られるはずなんだが、全然アイデンティティは保たれている。また、鬼便みたいに毛深くもならない。ただ、妖怪コンビが俺に何かが取り憑いていると証言し、獣のマルもそれを感じ取っていたのは確実な事だった。(12.4)
何の変化もないので、初めは警戒していたお紺たちも普通に接するようになった。
数日が過ぎ、ついに嗜好が変わってきた。もとから俺は肉食系だが、いよいよ獣の肉類が好きになってきた。鶏の唐揚げやヒレカツが好きだったのが、より咬みごたえもボリュームもあるステーキ肉などを欲するようになってきたのだ。しかもこれまではウェルダンの焼き加減を好んだが、血の滴るレアを求める気持ちがなぜか沸々と湧いてくる。
「シバラク食ベテナカッタカーラ、欲シイダケジャナイ?」
今夜のおかずは俺のリクエストに応えてTボーンステーキで、台所でそれを焼きながらマリアが言った。白人はそもそもレア肉をよく食うから、マリアにとっては俺の変化は取るに足りない事なのだろう。俺はその後ろで、肉の焼き上がりをワインを飲みながら今か今かと待つ。
「う〜ん、その可能性もあるけどな。」
まあ狼が乗り移ったからってレア肉好きになるだけで済めば罪もなかろう。さあ焼けたぞ。マリアから皿を受け取り、自ら食卓へ持っていって食い始める。左右に並んでいるナイフフォークを取ろうと思ったのだが、手が勝手に肉を直に掴んだ。そして手掴みでムシャムシャ!美味いっ!
「まあ行儀悪い!やめなさい、元ちゃんが見てるわよ!」
おゆき婆さんが咎める。
「ごめん、俺の意志じゃないんだ。身体が勝手に…」
言い訳をしながらも、口も手も止まらない。手掴み文化のインド人もビックリだ。あっという間に一皿平らげた。でもまだ物足りない。続いて焼き上がってきた隣のマリアと元の分に手を伸ばす。マリアにピシャリと手の甲を叩かれた。
「もうないの?」
「一人一枚シカ買ッテナイノヨ。サラダモ食ベタラ?」
「ちぇっ、しょうがねえか。」
無意識に手が食べ終わったTボーンに伸びた。動物のくせに器用にナイフフォークを操っているお紺がそれを見て、
「若旦ちゃん、骨まで食べるの!?」
「分かんねえ。ふと美味いかも知れないと思って。」
ステファニー、箸の手を止め、
「もしや犬神憑きの症状がとうとう現れたとか。」
「カキン!」歯が骨に当たって変な音がした。
「わーーーっ!歯が折れちゃった!」
「ホラ見ナサイ。調子ヅイテ、ソンナモノ食ベルカラ。」
舌で探ると右上の糸切り歯が欠けている。一気に食欲をなくした俺はごちそうさまをして、夕涼みに外へ出た。懐から煙草を取り出し、ライターで火を点ける。
「ふーっ…」
何気なく上を見た。空には中秋の名月が浮かんでいる。それを見た時だった。さっき欠いた歯の根元がむずむずしてきて、舌でいじっているとポロリと抜けた。続けて左の糸切り歯もポロリ。うわ!どうしよう!俺、歯茎は健康で歯槽膿漏の気なんか全くないはずなのに。
急いで家に入り、困惑しながらも玄関の姿見で前歯部分を観察していると、歯の抜けた穴がまたむずむずする。そこから何と牙がグングン生えてきた。
「ダーーッ!」
驚きのあまり「わあ」とか「ひい」とかの通常の驚愕の声も出ない。
「ダジゲデグレ〜!!」
と叫ぶ。家族が茶の間から出てきた。
「ドシターノ?」「どうしたの?」
「ほら、これ…」
俺は指で唇を上げ、歯を剥いて見せた。雪女と化け狐が顔を見合わせ、
「……やはり遂に。」
その時、遅れて出てきたおゆきが咄嗟に元を抱いて台所に逃げ込んだ。俺の異変を幼子に見せない配慮に違いない。
「《やはり》って何だよ。もしかして俺、狼男に?」
何か、不治の病を宣告されたみたいな絶望的な気持ちになった。だがそれどころでは済まなかった。今度は顔面がむず痒くなっててきて、思わず引っ掻く。ぎゃー!爪がかぎ爪に!!顔の皮膚からはたちまち無数の剛毛がワサワサと生えてきた。ドボチョーン!
続く(2016.12.5)
第四章
体毛の発生は顔だけに留まらず、見る見る数分間で全身に及んだ。ついでに耳まで尖ってしまった。
変わり果てた己の姿に、俺は泣いた。膝をついて崩れ落ちる。
「どうしよう、どうしよう…」
そんな俺をマリアが抱きしめた。このまま人間を捨てなければならないのだろうか。本能に振り回される他律的、非理性的存在者(※『実践理性批判』参照)に落ちぶれてゆくのだろうか。自己意識たる人類精神の一員(※『精神現象学』参照)ではなくなってしまうのだろうか。時間感覚もなくして、子供時代の思い出も将来の展望も消え失せてしまう(※『存在と時間』参照)のだろうか。マリアの伴侶の座を失い、その愛玩動物となってしまうのだろうか。もし有害になったら駆除されてしまうのだろうか。どことなく、いつものマリアの香りがおいしい獲物の匂いに感じてきた。
幸い、まだ言葉は話せる。妖怪コンビにかぎ爪の毛むくじゃらの手を合わせて懇願した。
「何とかしてくれ!お願いだから!」
ステファニーは焦ってもじもじしながら、
「えっと、お紺ちゃん、誰か除霊師知ってる?」
お紺、お前が頼りだ。ここ最近、からかってごめん。しかし、
「そういうのはちょっとね。狐憑きを払う奴って、あたいからすりゃ敵だから。」
するとマリアが俺の頭を抱きながら、
「私、エクソシストノ神父サマ知テルヨ。ニコラウス神父サマ。」
「その人呼べる?」
「サルディーニャニイルノ。パパァニ連絡シテモラッテソノ後ダカラ、何日カカカル。」
「それで間に合いませうか?」
「きっと、あんまり呑気にしてられないよ。時間が経つほど染み込んじゃうと思う。」
 次第に彼女らの話し声が、エコーがかかったように耳に遠く聞こえ始めた。俺は何かを感じ、衝動的に二階に駆け上がった。猛スピードで廊下の奥の物干し台に飛び出し、支柱をよじ登って瓦屋根の上に登った。おお満月だ。
次第に彼女らの話し声が、エコーがかかったように耳に遠く聞こえ始めた。俺は何かを感じ、衝動的に二階に駆け上がった。猛スピードで廊下の奥の物干し台に飛び出し、支柱をよじ登って瓦屋根の上に登った。おお満月だ。「ウオ〜〜ン!ウオオ〜〜〜ン!」
何という心地よさ、何という多幸感。俺は残っている理性の欠片で「何やってんだ俺?」と客観的に考えながらも、狼としての行動を抑えられなくなっていた。きちんとお座りして月に向かって吠える。
一同が追いついた。屋根の俺と物干しの女どもが対峙する。
「グルルルル…」
「まずい!逃げちゃうよ!」
「お紺ちゃん、捕まえて!」
「捕まえてっても自分以上に強いものには化けられ…。あ!」
 お紺がドロロン!大きな女郎蜘蛛に化けると、ステファニーが腕を取ってそれを宙に放り上げた。蜘蛛は尻からシューーッと蜘蛛の糸を吐き出し、俺の頭から浴びせかけた。
お紺がドロロン!大きな女郎蜘蛛に化けると、ステファニーが腕を取ってそれを宙に放り上げた。蜘蛛は尻からシューーッと蜘蛛の糸を吐き出し、俺の頭から浴びせかけた。俺は毛だらけの全身を粘性の強い糸でがんじがらめにされながらも、本能的にもがき暴れた。
「凶暴になりたり。これでは手のつけようもござらぬ。」
「もっと丈夫な鎖とかで縛ろうか。」
「麻酔銃がいずこかにござれば…」
「ソンナノ可哀想ダヨ。……イイコト考エタワ!二人トモ、チャント視テテネ。」
と、マリアはバタバタと階下に降りていく。間もなく家じゅうのありとあらゆる酒類を洗濯籠一杯に詰め込んで戻ってきた。
「ヨイショ、ヨイショ…。サア、ワカダンチャン。腹イパーイ飲ムガ良イ!」
「さすがマリアさん、若旦ちゃんの大好物で眠らそうってことね!ほれほれ、狼、こっちこい。♪こっちの水はあ〜まいぞ♪」
マリアがポン!とスパークリングワインの栓を抜くと、俺の五感は敏感にそれを察知、そろそろと物干しに降りて行く。
プシュ!お紺が缶ビールを開ける。
トクトクトクトク…、ステファニーは封を切りたてのウイスキーをグラスに注いだ。
こうなってはもう堪らない。理性の亡じた俺は欲望の赴くままに見境なく好きなだけアルコールをあおった挙げ句、酔いつぶれて寝た。
続く(2016.12.5)
第五章
朝になり、物干し台で目覚めると、俺は人の姿に戻っていた。さすがに二日酔いだったが。そしてその二日酔いの頭に、眠っている間に体験した夢のような何かが浮かんできた。タオルケットの中で懸命に記憶を辿る。
ああ!眠ってた時、俺は俺の中の狼と対話してたんだ。(思えばこれもテレパシー経験のおかげなのかも知れない。)
狼の話では、鬼便は薬で朦朧としてる時間が多いから、体毛を生やすなどのオオカミ化も比較的容易だったが、薬漬けが狼の体質に合わなかった。それに対し、俺は自我が強すぎて狼にはなかなかコントロールできなかった。だが、中秋の名月のタイミングで狼がわのパワーが増強され、一挙に俺の自我を圧倒してオオカミ化できたのだという。
真相は判明した。だからといって、俺がこのまま狼男として一生過ごすことはできない。月に一度くらいなら付き合ってあげれば良いじゃん、というようなことではない。だって、一度コツを掴んでしまえば、満月の夜だけでなく毎日でもオオカミ化できてしまうかも知れないじゃないか。
つまりだ。睡眠中には自己意識は減少する。いつも俺の眠りが浅い点は、寝てても自我は他人よりは強めに残っている道理だが、かのイギリス経験論の大物ヒュームによれば、自我なんて所詮《知覚の束》だってんだから(※『人間本性論』参照)、知覚が取り去られる熟睡中に、言い換えれば俺の意識の留守中に、心をいつ狼に占拠されても不思議はない。毎晩ステーキだと食費がかさむとかいう話ではない。恒久的に俺が俺でなくなってしまうのだ。たとえステーキ食ったって俺が食ってることにはならないのだ。(※こうしてみると、心身問題が近代哲学の祖デカルト以来のアポリアだという議論はよく分かる。)
朝のお茶をお盆で運んできたマリアは、俺が人の姿を取り戻したことで安堵している。
「アー、良カッターノ。」
「いや、安心するのはまだ早いんだ。」
俺はみんなに睡眠中の狼とのやりとりを話して聞かせた。
「かくなる上は、日中に何とかお祓いしなくてはなりますまい。」
「でもさぁ、すぐ来てもらえる除霊師はいないじゃん。」
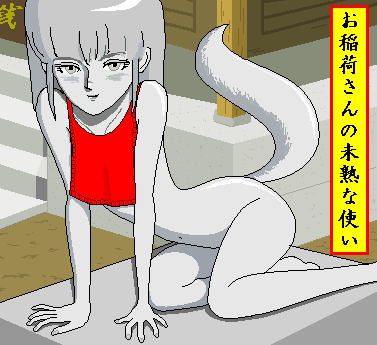 「お紺チャン、オ祓イデキルジャナイ。」
「お紺チャン、オ祓イデキルジャナイ。」「お稲荷さんの鳥居にかかったオシッコくらいの禍なら直せるけど(※『善悪の此岸』参照)、狼の魂なんて強敵は無理だよ。」
化け狐お紺は、お稲荷さんの使いとしてはまだ未熟者なのだ。
「じゃあ、俺がなるべく寝ないで頑張るから、その間に解決策を探してくんないか。」(12.5)
* * * * * * * * * *
と決意したものの、俺は酒飲みだ。酒を飲めば寝付きも良くなる。晩酌しちゃえばどうしても規則正しく夜には就寝してしまう。身体の健康は維持できても、その分狼に侵蝕される機会も増える。案の定、1週間ほどすると、夜な夜な体毛が増え、意識が戻る朝には消えるという症状が見られるようになった。被害が毛だけのうちに、本気で追い出さなければならない。
だがネットで除霊師を探しても、いざ来てもらうと、皆、役立たずどころかインチキばかりで、どいつもこいつも、精神衰弱してる人の弱みにつけ込んで金をむしり取るだけのペテン師だった。サルディーニャのエクソシストにも当たってもらったら、こちらは当地では篤く信用されており本物っぽかったが、ニコラウス神父はご高齢で極東までなんか来れないとのことだった。銀の銃弾だけなら送ってくれると言われたが、そんなことしたら俺も死んじゃうからお断りした。
夜の茶の間。
「なあ、お紺が俺に取り憑くってのはどうかな?で、その代わりに狼が出て行くとかさ。」
雪女「されど、狐憑きも恐ろしきものにござります。」
「でもさ、どこの馬の骨とも分からない見ず知らずの狼に乗っ取られるよりゃ、知り合いの狐の方がましだと思うんだけど。」
お紺「二つの魂が同時に入り込んだら、若旦ちゃんの人格は崩壊するよ。それでもいいの?」
「よくない。」
そんな人生の最終回、身も蓋もない。するとマリアが思いついた。
「ソシタッラ、ワカダンチャンノ心ガ強クナッテ、自分ノ力デ狼ヲ追イ出セバ?」
お紺「それ!それいいよ!」
続く(2016.12.11)
第六章
心を鍛えるったって、俺はそもそも意志堅固な方だ。坐禅で修養も積んでいるし(※『末世の凡夫』参照)、数々の逆境もはね除けてきているので、これ以上鍛える必要はないと思われた。しかしそんな俺でも狼を精神から追い出すことはできていない。こうなったら身体を鍛えよう。苦しいトレーニングを乗り越える過程で克己心も養われるに違いない。
早速、翌日からランニングと筋トレを開始した。道具がなくてもとりあえず始められるし、単調な種目だからサボろうとする弱さを振り払って立ち向かう甲斐がある。(12.24)
と思ったが、そうは問屋が卸さない。外堀の土手から靖国神社、北の丸公園といういつものコースをランニングしたが、狼が混入しているため、走り出したら止まらない。たちまち時速30kmくらいに加速し、同じ場所で練習していた大学の陸上部のコーチからスカウトされそうになったり、家で腕立て伏せでもしようもんなら畳に爪が刺さってしまって去年張り替えたばかりの畳表がズタズタ、という不経済な事態を招いてしまった。狼を追い出すどころか一層親和しつつあるのだ。
こうなったらやけくそだってんで、押入の奥から子供の頃買ったショッカーベルトを発掘して怪人の「オオカミ男」に成り切ったてみたが、つまらなかった。
このように努力しつつも困っている間に次の満月の晩が来てしまった。
馬刺しをつまみに晩酌して、飯を食うまでは良かった。黄昏の空にお月様がポーンと浮かぶ頃、俺の身体に再び急激な異変が生じた。
背中から始まって全身の皮膚がむずがゆくなり、毛穴からぞろぞろと灰褐色の剛毛が伸びてきた。俺はパタリと箸を落とし、我が手を見つめる。掌には肉球が浮かび上がり、かぎ爪がギラリ。鏡はないが、眼鏡が遠く見えるから既に鼻の先も長く伸びていることだろう。
その時、早くご飯を食べ終わり先に入浴していた元とマリアが風呂から上がってきた。
「ワカダンチャン、出タヨ〜。オ先ニイタダイタノヨ〜。」
わっ!元に俺の異常を知られてしまう!だがもう遅かった。
「わあー!しゅごーい!」
元は異形の俺を見て飛びついてきた。怪獣の扮装で遊んでくれるものと思ったようだ。
「こら!くっつくな!危ないから!」
まだ人間の理性は残っていた。自分の牙や爪で大事な倅を傷つけてはならない。俺は肘で元を押し退けた。不意を突かれて尻餅をつく息子。
元はニコニコしながら立ち上がる。遊んでもらっているとまだ思っている。
「やったな〜!そいだらシュペシュームこうせんだ。」
 風呂上がりの彼はウルトラマンの成り切りパジャマを着ていた。やや猫背の姿勢で、手を胸の前でクロスし、
風呂上がりの彼はウルトラマンの成り切りパジャマを着ていた。やや猫背の姿勢で、手を胸の前でクロスし、「ビビビビビビビビーーー!!」
「ガオーーー!!!」
俺も残余の父性を振り絞り、光線に撃たれなければならない。断末魔の雄叫びをあげ、白目を剥いて仰向けに倒れた。ばたり。死んだふり。
すると、底から突き上げるような衝撃を感じたかと思うとスッと身体が軽くなった。それを見ていたお紺とステファニーが虚空を指さして、
「あっ!狼が出て行く!」
何ということか、死んだふりの俺の身体から狼が抜け出ていくではないか!恐るべしシュペシュームこうせん!すごいぞウユトヤマン!
仰向けのまま天井を見つめていると、狼の気配を感じた。テレパシーを受信した。
「親子の情愛に負けたよ。俺にもかつて子供たちがいたことを思い出した。もうお前の暮らしの邪魔はしない。」
「この後どうするんだ?鬼便の所に戻るか?」
「いや、あんな奴はもう勘弁だ。この近所の猫のコニャロメというのがネズミも捕れないぐうたららしいから、それに取り憑いて鍛え直してやることにした。日本の獣には大和魂があることをたたき込んでやる。」
「まあほどほどにお願いしますよ。あれも飼い猫だから、狼の振る舞いが度を越したら飼い主が迷惑するからね。」
転がっている俺に元がのしかかってきた。ああ、そうだった。ウユトヤマンを飛ばしてやらなくちゃ。
完(2017.1.5)
