第一章
春は近い。春といえば、そう花粉症だ。自慢じゃないが俺の花粉歴は長い。最初期には相当苦しんだもんだったが、近頃は良い薬が開発されて昔ほどは来る日も来る日も鼻グズグズという状態ではなくなった。それでも杉花粉の最盛期にはクシャミ、鼻水、鼻づまりは避けられない。さらにこの時期の必需品であるマスクも良し悪しで、眼鏡の人間にとっては呼気でレンズが曇ることがこれまた避けられない。今、マスクで防備して島政に出勤する途中なのだが、少し寝坊したので急ぎ気味に歩っていたら案の定レンズが曇ってしまった。往来の真ん中で立ち止まっている訳にいかないので、路地に入って眼鏡とマスクを外し、尻ポッケからハンカチを取り出して、息をハーと吹きかけて拭いた。そもそも眼鏡が曇ってるのにハーとやるのもバカみたいだが、習慣だからしょうがない。その時だった。
「だーれだ?」
後ろから目隠しされ声をかけられた。
「バレバレだよ、お紺。」
「あれっ?声色使ってたのになあ。」
俺は目隠しの手首を掴み、振り向いて狐娘の顔を確認した。
「お前には獣くささがあるんだよ。だからどんなもんに化けたって、鼻の利く俺様にはお見通しなんだ。」
「鼻で分かるのに何で『お見通し』なのさ。お見通しなら目で分かるんじゃなきゃ。」
「屁理屈を言うんじゃねえ。そんなら『嗅ぎ通し』だ。でも、嗅覚も視覚も同じだよ。嗅覚は匂い物質が神経を刺激するから感じるんだけど、視覚だって目の触覚だぜ。触れない距離の遠くにある物を見てるように思ってるが、光が水晶体を通過して網膜に到達するから見えるんだ。」
つい哲学的な話になるのが俺の悪い癖。無論、お紺には理解できない。だから聞いちゃいない。お紺は話を戻す。
「ねえ、あたいそんなにくさい?シャンプーとかしてるんだけどなあ。」
「人一倍嗅覚が鋭いから俺には分かるけどね。他の人は知らねえな。まあせいぜい気をつけな。そんな娘の格好してんだからな。」
「でも花粉症でよく匂いが分かるね。」
「今んとこ快調だから。これも抗アレルギー薬『アレキサンドリア』のおかげだ。」
「何か立派な名前。高いの?通信販売?」
その瞬間、いきなり鼻がむずむずしてきて、
「ェヘーーーックシイッッ!!…タハ」
(※これは厳しいくしゃみだった。もとはと言えば、花粉症の話なんかするから鼻もその気になるんだ。我々花粉症族は、ニュースや薬のCMで花粉の飛散シーン観ただけでむずむずするものなのだ。条件反射だね。パブロフの犬だね。)
治まったかと思いきや、間髪を入れずまたむずむずの波が抗いがたく鼻粘膜を襲う。
「ハヒ…ハヒ…ヘーーーッシイッッ!!イェーーーーーーッグシイッッ!!」」
3連発だった。今度はジャンパーのポッケからティッシュを取り出し洟をかんだ。
「こえれじばんどぎゅ~がぐぼしばなぐおやふびら、やでやで(=これで自慢の嗅覚もしばらくはお休みだ、やれやれ)。」
「人間は気の毒だね、あたいには関係ないもんね。」
「へえ、のうむすはだいろ?かうんしょ(=へえ、動物はないの?花粉症)。」
「さあ。だってあたい妖怪だもん。」
この言葉で俺は思いついた。
「おごん、たべしりおえりろりついれびれぐんだい(=お紺、試しに俺に取り憑いてみてくんない)?」
「何で?」
「らからかうんしょらおうかぼしえらいらん(=だから、花粉症治るかも知れないじゃん)。かうんしょららいぼろりろりつがえれわ(=花粉症じゃないモノに取り憑かれれば)。」
お紺はちょっと考えて、「……じゃあ後ろ向いて。」
言われるままにお紺に背を向ける。
「はい、そしたら目をつぶって。」
目をつぶる。すぐ後ろに気配がする。耳の辺りに両手が伸びてきたような感覚がある。すると、

「むぎゅ」
という擬態語とともに、お紺が俺の顔を変顔にした。
「らいひやがんりー!(=何しやがんでい!)」
カッとなった瞬間に鼻は通ったのだが、口許を横に引っぱられているため正しい発音ができない。『がっきゅううんこ(=学級文庫)』が懐かしい。
「わ!鼻の穴に指が入っちゃった。汚~い!」
「わはははは!はらびるれすうぇったら、わかなやち(=鼻水で滑ったな、バカな奴)」
「あの、もう手は離してるよ。普通にしゃべれば。」
「あ、そう?何か変だと思った。……そうじゃない!何で変顔にすんだこの野郎!」
お紺は憤る俺をたしなめるような落ち着いた口調で、
「あのねえ、本当の狐憑きって恐ろしいんだから。ダダの着ぐるみ(※『樹海文書』参照)なんてもんじゃないのよ。気がおかしくなるかも知れない。」
そりゃそうだ。古来『狐憑き』といえば精神錯乱した人の呼び方だ。しかもこんな未熟な狐の妖術じゃ、もとに戻れない可能性もある。花粉症完治作戦は幻に終わった。
「だからって人の顔で遊ぶな。」
「ごめんごめん。面白そうでつい。」
他愛ない悪戯は俺も好きだ。輪ゴムの指鉄砲とか、ストローの袋の吹き矢とか、単純に面白い。大人げないと言われても面白いもんは面白い。だからこれ以上お紺を責めることはしなかった。だが内心では、近いうちに必ずリベンジしてやるぞと、路地から垣間見える朝の青空に固く誓った。
続く(2016.3.13)
第二章
「お前、先ぃ歩きな。」
「その手は桑名の焼き蛤、見え見えよ。どうせ後ろから変顔のチャンスを狙うんでしょ?」
「そんな見え透いた手、使う訳ないだろ。バカじゃねえか。」
実は図星だった。まあいい。一日はまだ始まったばかりだ。
「じゃあ仲直りの握手しよう。」
「嫌だよ。手を出したらどうせつねるんでしょ。親指と人差し指の間の皮んとこ。」
「どうしてお前はそうひねくれてるんだ。」
実は図星だった。
「ところでさあ、身体の中で一番臭い所ってどこか分かる?」
「知ってるよ。どうせ手の平だって言って、自分で嗅いでみろとか言って、鼻先に手をかざしたらその後ろから手を押して鼻にぶつけるんだから。ひっかからないのだ。」
「手の平が一番臭いわけないじゃねえか。何言ってんの?」
実は図星だった。
「クリームパン食べない?」
「要らない。どうせさっきの鼻紙でしょ?」
実は図星だった。
「じゃあじゃあ、『手袋』の反対、言ってみ?」
「もうやめとけば。」
当面ネタ切れだ。真面目に仕事しよう。
* * * * * * * * * *
今日は親父と雪女が市場に買い付けに行く番なので、俺は遅めの出勤だった。シャッターを上げ、野菜を所定の位置に陳列していたら、ふと高校時代の夏合宿の記憶が甦った。
俺の一つ上の先輩の辺りからおならの臭いがしてきた。俺の同級生が先輩を疑って、
「守谷先輩、今おならしたでしょう!」
ところがその先輩、いたく立腹し、
「してねえよ!疑うんなら嗅いでみろよ!!」
と逆ギレした。しかし友達も引き下がらない。「じゃあ」と言って、鼻を先輩の尻の至近距離まで近づけて、よせばいいのにそこの空気を思い切り吸い込んだ。そしたら実際に犯人はその先輩で、もろに臭気を喰らった友達は、
「う!くっせえ!すんげえくっせえ!ゲホゲホ!やっぱ守谷さんじゃないスか!ゲーホゲホ!」
みんなで大笑いした。我ながらバカな高校時代だった。
先ほどの『身体で一番臭い所』ネタからの連想でこのエピソードを思い出したのだが、そこからさらに連想が広がった。そうだ!ブーブークッションでお紺をだまそう。いっひっひ。
あの玩具はなぜか笑える。自発的にやってみても笑ってしまう。あの湿った音が絶妙に可笑しいのだ。笑いを誘発する強度では、昔懐かしの『笑い袋』と双璧をなすのではなかろうか。
休憩時間、煙草を買いに行くついでにおもちゃ屋に寄った。もちろんブーブークッションを買いにだ。俺の小さい頃からやっている店で、最近では元とお散歩する度に怪獣のお人形を買ってやっている。俺も親父に休みのたんびにここで怪獣買ってもらったっけ。歴史は繰り返す。
「今日は坊や一緒じゃないんだね。お土産ですか?」
「いやブーブークッションください。」
が、そんなもの今どき置いていないと言う。そりゃまあ時代遅れだわな。寂しいご時世になったもんだ。あっさり諦めて店を出たら、すぐあとから主人が追いかけてきた。
「島政さ~ん!あったあった!女房が倉庫にあったのを思い出したんですよ。」
おおそうですかありがとう、と店に引き返して代金を払い、帰途についた。(3.13)
高揚した気分で島政に着き、店先で丸椅子に腰掛けていたステファニーに、
「待たせたね。ただいま。」
「お帰りなさいまし。今日は晴れてるのに暇でござる。」
「お紺は?」
「はて、存じませぬ。さっきまでそこでワサビの仕分けをしておりましたが。」
「まあいいや、休憩交代しよう。今、お茶にするからな。」
 帳場の小上がりの座敷を覗くと、お紺は隅でうたた寝をしていた。形姿は人に化けていても眠る時は狐らしく丸まってるから面白い。すやすや寝息を立てている。ぐっすり寝てるみたいだ。しめしめ、罠を仕掛けるにはうってつけのタイミングだ。今のうちに座布団の下に…いっひっひっひ。
帳場の小上がりの座敷を覗くと、お紺は隅でうたた寝をしていた。形姿は人に化けていても眠る時は狐らしく丸まってるから面白い。すやすや寝息を立てている。ぐっすり寝てるみたいだ。しめしめ、罠を仕掛けるにはうってつけのタイミングだ。今のうちに座布団の下に…いっひっひっひ。感づかれないように裏口に出てブーブークッションのパッケージを開き、包みをゴミ箱に捨てる。中身を腹巻きに仕舞って屋内に戻る。台所の戸棚から菓子を取り、急須と茶碗と一緒にお盆に乗せて座敷へ向かう。盆をそっと卓袱台に置いて、腹巻きからブツを取り出して普段お紺の坐る定位置にある座布団の下に忍び込ませる。お互い取り決めた訳でもないのに一定のメンバーの間では自ずと定位置が決まるってのもありがちでいて不思議な話だが、罠を仕掛けるには好都合じゃないか。仕掛けをする間、実際の場面を想像するだけでこみ上げてくる笑いを堪えるのに苦労した。
さて準備は整った。ぼちぼちお紺を起こして、恥辱のブーブー座布団の刑に処するとしよう。(3.16)
俺は俺の定位置に陣取り、
「おいお紺、おやつだぞ。」
と声をかけたら、ピクリと耳を動かし、やがてむっくりと起き上がった。
「あー、ごめんなさい。寝ちゃったみたい。」
早く坐らせたいが、戦略を悟られてはならない。あくまでも日常生活を演出しなければ。
「『みたい』どころかグースカ寝てたじゃねえか。あ~あ、よだれ垂れてるぞ。」
「えっ!?」
と焦った表情で手で唇を拭った。
「わははは!バカが見る~、ブタのケツ~!」
お紺は「もう!」と言ってふくれた。からかいに引っ掛かってざまあみろと思ったが、まだ生ぬるい。俺のリベンジはこんなもんじゃ済まないぞ。見ているがいい。ヌハ、ヌハ、ヌハハハハハ!
「おやつだから食べな。」
「わーい!」
と、自分の定位置に着く。座布団に坐った!
続く(2016.3.19)
第三章
………ん?ブーブークッション鳴らないぞ?お紺はしっかり座布団に尻を乗せているのに。確かにこいつは狐だから体重は軽い、それにしても鳴らないはずは…。
まさかの故障?何年も在庫品で古道具みたいなおもちゃだから、もしかしてゴムとかが風邪引いてて(=「劣化していて」という意味)、排気口というか弁というか、あそこが癒着しちゃってるのだろうか。どっかに穴が空いてたとか?ブーブークッションのくせにすかしっ屁をするはずはないから何らかの故障だな。しかし、現時点では具合を確認することもできない。
お紺は手早くキャラメルコーンを口に放り込み、お茶をすすって立ち上がった。
「ごちそうさま。ステファニー、店番交代しよ~!時間遅れちゃってごめ~ん。」
と表に駆けていく。
今だ!ブーブークッションの機能を確認するには今しかない。お紺の座布団の方にいざり寄った時、入れ違いにステファニーが座敷に入ってきた。俺は動きを止めた。雪女は菓子皿を見て、
「私、キャラメルコーン大好き。」
と嬉しそうな顔をした。そしてよりによってお紺の坐っていた場所に坐ろうとする。
「あっ!ダメダメ!」
俺は手を伸ばして遮ろうとした。
「なぜそんな意地悪言うの?雪女がキャラメルコーン好きじゃいけないのでせうか?」
「そんなんじゃなくて……あの、そこに坐るな。」
と答える暇もないうちにステファニーは座布団に正座した。そしたら、
「ブーーーーッ!」
とおならの音がした。虚ろな目で凍りつく雪女。静寂が小上がりの四畳半の座敷に広がる。
「えっ?えっ?何?…私、何も…。」
顔を真っ赤にして震える雪女。すがるような眼差しで俺を見るその目から大粒の涙が溢れ出す。
「ちちちち違うんだ!お前のおならじゃない!」
「では若旦ちゃんの?グスン…」
「あいややややや!俺じゃない!そうじゃない!えーと、おならじゃない!」
無辜の民を傷つけてしまった俺は激しく動揺している。
「だっ、だから、そこにブーブークッション置いたんだ。」
雪女は怒りとも嘆きともつかぬ顔になり、
「ひどいわ…」
と両手で顔を覆った。どうしよう。
「ご、ごめん。悪かった。悪気はなかったんだ…。お前を傷つけるつもりなんて…。」
「悪気がなくてこんなことするの?あんまりだわ。」
「そう、悪気はあったんだ。いや、なかったんだ。本当ごめん。」
思わず、すすり泣くステファニーの肩を抱いた。
「いやっ!汚らわしい!触らないで!」
激しく拒絶し俺の胸元をどついた。俺はひっくり返って後頭部から土間に転げ落ちた。
目から火花が散ってクラクラしていると、そこにもう一人雪女が入ってきた。
「あれ?」
雪女は俺を見下ろし、
「どうなされたのですか?若旦ちゃん。」
「だって……。あっ!!お紺だな!」
 座敷の方の雪女が立ち上がり、
座敷の方の雪女が立ち上がり、「キャハハハハ!今頃気づいたか!ブーブークッションなんていう古典、あたいが見抜けないとでも思ったか。お紺ちゃんはだまされないのだ。」
と勝ち誇って、ドロロン!と狐娘に戻った。
「畜生!」
俺は土間を叩いて悔しがった。この恨み晴らさでおくべきか。
続く(2016.3.19)
第四章
部分的な現象だけ見れば、雪女に化けた狐娘が自分の尻でブーブークッションを鳴らしたのは事実である。だが、俺が引っ掛けたことにはならない。奴は確信犯で鳴らしたのだから。逆に俺が化かされていたのだから。土間に後頭部を強打したのだから。
相手は何たって本職だ。『化かし』のテクニックでは狐に敵わないのだろうか。だからといって万物の霊長がイヌ科ごときに負けるなんてことはあってはならない。
でもよくよく考えると、人間が動物に勝るのはせいぜい道具を作れる点だけだ。道具の力で森を切り開き、野生動物を駆除し、人間のための世界を築いてきたのである。それに比べて、狐は身体一つで頑張っているんだから見上げたもんだ。
と、一時は謙虚な思いにもなったのだが、個人的なルサンチマンは別である。俺は狐が憎いのではない、お紺という個体に遺恨があるのだ。たとえニーチェからルサンチマンの持ち主が下劣な奴隷道徳を生み出し価値を捏造するのだと批判されたって、あるったらあるのだ。
改めて復讐のアイデアを練ろう。
①物陰に隠れて、後ろから「わっ!」とか言って驚かすか。つまらないな。
(※ちなみに、こういうケースで驚いた場合、大人も子供も大抵の人が「あびっくりした~」と反応するが、常々これが不思議だった。驚愕するという一瞬の反応のわりには「あびっくりした~」は長すぎる。「あっ!」だけで終わらないのはなぜなんだろう。先日飲み屋で考察したら、店の馴染みの娘は、最初の「あ」が驚きで「びっくりした~」の部分は感想だというのだ。言われてみれば確かに、「あびっくりした~」と口をつく場合は、驚かした相手が親しい人物のときである。まさか、テロリストにもし拳銃を突きつけられても「あびっくりした~」とは絶対言わない。彼女の洞察力はなかなかのものである。)
②眠っている間に顔に落書きするか。でもさっき昼寝したばかりだからしばらくは寝まい。
③UFOが出たとかホラ吹くか。でも化け狐だって超常現象だ。
④悪戯の王道『スカートめくり』!でも奴は尻尾でがっちりガードしているしな。第一、いい年こいてそんなことしたら却って俺が変態に思われてしまう。変態扱いはまっぴらだ。
⑤カレー味のウンコでも食わせるか。でもそんなもんどうやって作るんだ?
⑥それならおびき出して犬の糞でも踏ませるか。でも今どきは滅多にお目にかからない。
 ⑦バナナの皮を地面に置いといて滑らすか。でも漫画以外で本当にバナナで滑った奴を見たことがない。
⑦バナナの皮を地面に置いといて滑らすか。でも漫画以外で本当にバナナで滑った奴を見たことがない。(※またちなみにだが、「ギャフンと言わせてやる」という慣用句がある。だが実際に「ギャフン」という台詞は聞いたことがない。)
⑧ピンポンダッシュはどうだ?でもお紺が住むのは俺の家、何の意味もない。
う~む、いずれも決め手に欠けるなぁ。
店先で腕組みして考えあぐねていると、二階から親父が降りてきた。
「ああ、もうおやつにしたのか。」
とつぶやきながら、座敷に入っていく。危ない!そこにはブーブークッションが!慌てて座敷へ急行する。だが時、既に遅し。
「ブ、ブビューーーーッ!」
高らかに鳴り響く屁の音。
いい大人が何やってるんだと、こっぴどく怒られるかと思いきや、さすが俺の親だけあって洒落は通じる。怒るどころかゲラゲラ笑って、お袋を引っ掛けたらどうなるかななどと面白がり、クッションを持って二階に上がっていった。
そのうちお袋がレジ袋下げて買い物から帰ってきた。豚肉を安売りしていたと上機嫌で、多めに買ってきたからあんたの所にも持ってお帰りとか言って奥の台所に向かう。いくつになっても母親というのは有り難いものである。
「お袋、二階じゃ座布団に気をつけた方がいいよ。」
とさり気なく忠告した。真意が伝わったかどうかは分からない。はっきり告げ口した方が母のためかも知れない。しかしながら他方では、父の遊び心を踏みにじることは俺にはできなかったのだ。
程なく二階から、親父の笑い声に続いて、お袋が親父を叱責する怒声が聞こえてきた。親父は成功したと見える。これも夫婦円満の偉大な刺激剤であろうか。
そうこうするうち店が忙しくなってきて、いつの間にかリベンジは忘れてしまった。
続く(2016.3.19)
第五章
夕焼け小焼けで日が暮れて、閉店の時間となった。その日の売り上げを勘定し、仲買に明日の注文の電話をして家に帰った。
今日はいろいろと頭を使ったんでくたびれた。それに今日は一日好い天気でかなり花粉は飛散していたはずだから、きっと全身に花粉が付着しているだろう。いつもは晩酌の後に風呂に入るんだけど、今夜は先にひとっ風呂浴びよう。花粉を洗い流してさっぱりしてから一杯やってぐっすり寝るとしよう。
ふ~う、極楽極楽。イイ湯だなアハハン♪
良い気分で風呂を出た。脱衣所で髪を拭いていたら、突然ザシャーッと、廊下と脱衣所を仕切るアコーディオンカーテンが開いた。反射的に振り返る。下着姿のお紺が目を丸くして立っている。両者、一瞬凝固する。

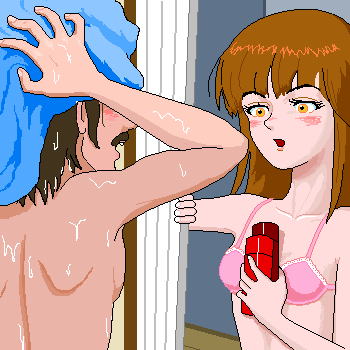
「キャーーーッ!」
と叫んで、お紺は胸に抱えていた物を俺に投げつけてきた。
「痛てっ!何すんだこの野郎!」
俺の頭と腹にぶつかり床に落ちたのはスーパーリッチなシャンプー&リンスだった。
「若旦ちゃんのバカ!」
と言い捨ててお紺は居間の方に逃げていった。急いで浴衣を羽織り俺も続く。
「ドシターノ?」
明らかに様子がおかしいのでマリアがお紺に尋ねた。
「死ぬかと思った。」
「ワカダンチャン、マサカお紺チャンヲ?!」
「違うよ!!俺の方が被害者だ!お紺、てめえそっちが勝手に人の裸を見といて、何だよその言い草は!」
「だって…」
「朝、視覚は目の触覚だって言っただろ。お前は俺のを目で触ったんだ。」
「だったら若旦ちゃんだってあたいのブラとか見たじゃんか!そしたら触ったってことじゃんか、エッチ!」
「てめえこそ、脱衣所の前でいちいち下着姿に化けなくたって、風呂場入ってから一遍に狐に戻りゃいいじゃねえかバカ。」
マリア、事態が大体飲み込めたようで、落ち着き払って、
「マア待チナサイ。目ハ触覚イウノワ、生命ノ発生シタ頃ワ光ヲ感知スル器官ワ触覚ノ一部ダッタダロウ話デショ。」
「マリア、お、お前、どこでそれを…」
「コンナノ当タリ前ナノヨ。L'ÉVOLTION CRÉATRICEナノヨ。」
「へへぇ~!お見それ致しました。」
「ワカレバヨロシイ。今後ワ露出狂ワ慎ムヨウニ。」
「違うって言ってんだろ!!」
マリアの見識には恐れ入ったがそれはそれとして、この事件の経緯はこうだ。お紺は今朝俺に獣くさいと指摘されたのを気にして、汗を流そうと思い、俺がイレギュラーな時間帯に入浴しているとはつゆ知らず、脱衣所の戸を開いたのだった。ところが不意にすっぽんぽんの俺が目の前に現れてびっくり仰天、というワケ。
さっきはお紺を非難したが、実のところ、こっちは見られたからって減るもんじゃなし、別にへっちゃらだ。「へのちゃら」ってやつだが、お紺は意外と純情だったようだ。
図らずもお紺を動転させる野望が叶ったのは結構である。ただ、その手段が、全裸を開陳するという『飛び道具』、というか下ネタだったことは甚だ遺憾とするところである。
完(2016.3.19)
と、完結したものの、その後、書き始めた作品が「後日譚」にふさわしいものになってしまったので、
『治療不可』後日譚 Difficult to Cure
第一章
前話以来、お紺と俺の化かし合いは続いている。昨日は煙草の箱の中の一本がタバコチョコにすりかえられていた。さすがに重さも形も違うので火を点ける前に気がつき、昔懐かしく美味しく頂いた。だからこっちは今日、テレビの罰ゲーム的な、多量のワサビを中心部深く忍ばせた稲荷寿司をうまくちょろまかして狐に食わせた。好物だから警戒心が緩んだものと見える。かぶりついてから少ししして「コーン!」と鳴いて飛び上がり、ひとしきり苦悶してから涙目になっていた。勝った俺は、
「俺と勝負しようなんて百年早いんだ。おとつい来やがれ!」
と、僭越にも四百歳ほど年長のお紺に言い放ったのだったが、相当悔しがっていたお紺が今度はどんな手に出るか予断を許さない。
夜中、寝苦しさで目覚めた。首から胸元を探ると汗をかいている。まだ四月だぜ、軽い羽毛布団が負担になる季節にはまだ早い。普段、春眠は暁を覚えずぐっすり眠れるんだけどな。飲み過ぎたかな?風邪の引き始めかな?あ、花粉症の薬のせいかな?
とここまで目をつぶったまま考えて(※俺は夜中に目が覚めても、いつもこの程度は瞬時に思考できるのだ。ただしこれは自慢でも何でもなく、単に眠りが浅いだけだ。)、布団を矧がした。ところが、矧がした布団がまた俺に覆い被さってくる。
「むわっぷ!」
意識をさらに覚醒させると、布団の香りがスーパーリッチなシャンプー&リンスのそれであることに気づいた。
「おいこら、てめえ、お紺だな?」
「う~ん……ムニャムニャ…」
元の声だ。俺たち親子は仲良し小好し。いつでも一緒にポックリポックリ♪…じゃなくて、いつでも一緒に「川」の字で寝ているので、深夜突然の俺の声で隣の元がむずがりかけたと思われる。
 小さい声でもう一度、
小さい声でもう一度、「てめえお紺だろ?」(※小声は小さいポイントで表記します。)
月明かりの下、掛け布団に向かって声をかける。するとその一部がお紺の顔になった。
「やっぱバレた?これがあたいの『熱死大作戦』だ。参ったか。」
「なにバカなことやってんだ。早くどけよ。明日、朝早いんだから。」
「あたいが良い匂いになったの分かる?」
「どうせスーパーリッチなんだろ?でも安眠妨害だぞ。これ以上どかねえと知らねえぞ。」
「お紺ちゃんの『熱死大作戦』を逃れた者は未だかつていないのだ。」
「しゃらくせえ。ならばこれでどうだ。」
お紺の化けた掛け布団を鷲掴みにすると同時に、ブッ!俺は布団の中でおならをした。
「あっ!…ブホ!ゴホゴホゴホ!離して!もう勘弁!」
暴れる掛け布団。
「ワハハハハハ!見たか忍法『へのいちの術』!」
臭いに耐えかねてお紺は布団から人間の姿に変わった。その時、「川」の字の向こう側のマリアが枕元の電気スタンドを点け、半身を起こして俺たちを見た。
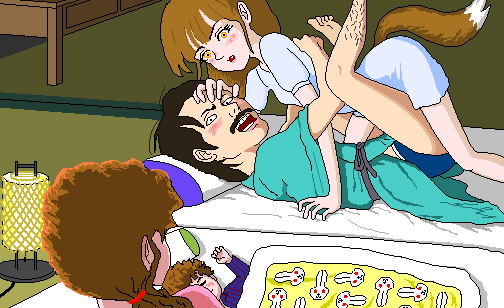 「ワカンダンチャン!アナタワ一体ナニヲ…、ソンナ人トワ思ワナカッタ……。」
「ワカンダンチャン!アナタワ一体ナニヲ…、ソンナ人トワ思ワナカッタ……。」俺と狐は不可抗力で抱き合った状態になっていた。
「お紺チャンマデソンナニ嬉シソウニ尻尾フッチャッテ…。コナイダ、二人ガオ風呂出テキタ時、気ヅクベキダダノネ……」(※前話参照)
「全くの誤解だ!」
お紺が「ちっ!バレたか!」
「何言ってんだ!『バレたか』じゃないだろ?バレちゃいねえだろ?バレるようなことなんかしてな…。ええい!この化け狐、俺から離れろってんだ!」
お紺を突き飛ばす。マリアは絶望的な目つきで、
「マダ白ヲ切ルノ?言イ訳ナンカ聞キタクナイ!コンナニハッキリバレテテテ!」
「でも本当、バレてないんだよ!!あ~!違う違う、そのそのその…バレるとかさ、そういう次元じゃなくってさ。」
「開キ直スノネ!」
「『開き直る』だよ、それは。」
「ソヤッテバカニシテ……モウイイノヨ!!」(2016.5.2)
そう言うと、マリアは壁側にある桐箪笥を向いて衣類を取り出し始めた。
「私、トスカーナニ帰ラセテイタダキマス。」
「わー待て待て!誤解なんだから。今、ちゃんと説明するから。」
「長イ間オ世話ニナリマシタ。幸セダタワ。元ワ連レテクカラ。」
「だから話を聞いてくれっつーのに!」
にじり寄ってマリアの腕を掴んだ。すると背後から、
「だって若旦ちゃんがあたいにしがみついて離さないんだもん。」
「そうやって一部分だけ報告するなよバカ狐!俺はおならを嗅がせようと…」
マリアは俺の手を振りほどく。
「ヤパーリ二人ワ出来テルダタノネ!オナラシテモ大丈夫ナ仲ニ。ハレチンダワ!」
「違う!全部が違う!まず『ハレチン』じゃなくて…」
その時バン!と襖が開いた。奥の部屋のおゆき婆さんが仁王立ちしている。
「こらっ!こんな時分に何の騒ぎだい!ご近所迷惑じゃないか!」
「は~い…」
婆さんの一喝で落ち着きを取り戻した一同は、元を起こしちゃいけないので下に降り、居間で話し合った。
マリアの誤解はすぐ解けた。要するに、俺とお紺がいつまでも化かしっこをしてるのがこのような悲劇を生んだのである。平和条約を結ぶ時が来たようだ。
ただ、一つ疑惑が残る。今夜、お紺が布団に化けて寝室に忍び込んでいたということは、日頃の俺とマリアの営みも覗かれていたのではないだろうか。だがそれを面と向かって聞いてはお互い恥ずかしいことにもなりかねない。ここは遠回しに探りを入れてみよう。
「そういや、お紺はいつもどこで寝てんだっけ?物干しだっけ?」
 「大抵はネズミを求めて夜の街に出てるわ。地下鉄の構内をねぐらにしてる奴が結構いるのよ。あたいは夜の女。『牛込の銀狐』って呼ばれてるの。」
「大抵はネズミを求めて夜の街に出てるわ。地下鉄の構内をねぐらにしてる奴が結構いるのよ。あたいは夜の女。『牛込の銀狐』って呼ばれてるの。」と言うと、気取って鼻面を上に上げた。
「あはははは、誰からだよ。単に夜行性なだけだろ?あと『牛込』ってのが今イチだな。そうだ。あだ名なら『有楽町線のお紺』なんてなぁどうだい?ちょいと粋じゃない?」
「うるさいなあ。それじゃスリの親分みたいじゃんか。でね、帰ってきたら縁の下で食休み。至福のひと時ね。」
考えてみれば、狐はもともと巣穴好き。どうやら夫婦の寝室には興味ないらしい。安心した。
「よし仲直りだ。もう化かすのはやめにしよう。」
「え~!仲直りは良いけど、化かしは妖怪の本分、やめるなんてできないよ。」
確かにそうだ。お化けは化けなきゃお化けじゃない。『お・け』だ。お間抜けなお化けだ。
「だから間抜け」
「何!?」
「いや失礼。えーとつまりさ、勝負に使うからいけないんだ。平和利用すればいいんだ。」
「化カシヲ平和利用?デモ化カスッテ、騙スコトデショ?ナンカ変ジャナイ?」
「『化かし』の概念からすりゃ矛盾してるけど、この被爆国が原子力を率先して使ってるのに比べりゃ、そんな矛盾かわいいもんだろ?」
「う~ん、何だか分かんなくなってきた。」
柱時計が三つ鳴った。
「ありゃ、もう3時じゃねえか。あと1時間しか寝れねえや。とっとと寝ようぜ。」
今朝は俺が市場に買い出しに行く番なのであった。
続く(2016.5.3)
第二章
さて、その日の夕方。
俺は帰りがけに、飯田橋駅前の旅行代理店で、モンゴルのパンフをもらってきた。夏に行こうと思っている旅行先だ。居間で夕飯が出来るのを待つ間、熟読した。
「乗馬体験だって。俺、馬に乗ったことないんだよな~。ゾウとラクダには何度も乗ってるのに。」
「へえ、いずこにて?」
箸を並べに入ってきた雪女が尋ねる。
「ゾウは、インドとタイとネパール。ラクダは敦煌とカイロで。」
「すごいですね。でもいよいよ馬のチャンス到来で、祝着至極に存じまする。」
「うん。楽しみだなあ…」
『モンゴルの馬はおとなしく、すぐに乗れるようになります。』と書いてある。思えばゾウは御者付きだったし、ラクダもこっちはただ乗っかってるだけで別の人が引っぱってくれてたんだ。一人で操縦してた訳じゃない。それと比べて乗馬は独り立ちしなければならないようだ。ガキの頃、自転車の補助輪外すのも他人より遅かったしな。ここは一発、日本で練習しておいた方が良いかも知れない。俺は『化かし』の平和利用を思いついた。
「お~いお茶、じゃなかったお~いお紺!」
(※ちなみにこの『お~いお茶』という有名なコピーは、お茶を呼んでいるのではない。お茶を持ってくるよう古女房に指示を出しているのである。言語使用という行為は理屈抜きで行われるのだ。『規則は行為の仕方を決定できない』とヴィトゲンシュタインも論じている。〔※『哲学探究』参照〕)
「なあに?」
雪女と入れ違いに、お新香の鉢を持ってお紺が居間に入ってきた。
「なあ、お前、馬に化けてくんない?」
「へ?馬?どうして?あっ!さては昨夜みたくあたいに馬乗りになって欲しいんでしょ、ウフフ。」
「バカタレ!本当の馬!乗馬の練習したいんだよ。何が『ウフフ』だ、この擦れっ枯らしめ。」
「ん~、馬か…。馬は無理だわ。」
「何で?『化かし』の平和利用だぞ。頼むよお紺ちゃん、ご褒美に油揚げ買ってやっから。厚揚げだっていいぞ。」
「あんな何十倍も大きいのになんか化けられないよ。自分より小さいのだったら得意なんだけど。」
「そうなの。ちぇっ……。そうだ、お~いステファニー!」
「如何なされました?」
「馬の脚になってくれ。それでお紺は馬の上半身に化けろ。」
いわゆる《ドドンゴ》(※ウルトラマンに出てくる伝説の麒麟みたいな怪獣。役者が二人がかりで一体の着ぐるみに入って演じる)の形を二人で作ってもらいたいのだ。
「馬の上半身って何さ?」
「首から前脚まででいいから。」
 お紺は上半身は人間、下半身を馬の前脚だけに変身させた。
お紺は上半身は人間、下半身を馬の前脚だけに変身させた。「う~ん、そうじゃないんだなぁ…。それじゃ出来損ないのケンタウロスだよ。でもまあよしとするか。それで胴と後ろ脚はステファニーがやるんだ。こう、前屈みになってお紺の腰の所に頭を付ける。」
「成程。されどそうなると、若旦ちゃんが乗るのは私の背中、重たいの嫌でござりまする。」
「1回だけ!1回だけだからお願い!重いったって55kg切るんだぜ。その代わり、ハーゲンダンチョネの新種のアイス買ってあるから食べなよ。」
「新種?もしやコスタリカのコガネ虫とか蝿とか珍しい昆虫を混ぜ込んで…」
「いやいや、海ブドウの泡盛味。ブランデーレーズンの真似かもな。」
「ほお~、それはそれは私の愛でるトロピカルなフレーバーでござりませう。」
「だからやってくんねえかなぁ、馬の脚。」
と俺が妖怪を拝み倒しているところへ、飯の支度の間、お散歩に連れ出されていた元が婆さんと一緒に帰ってきた。
「オトーシャン!オウマサンして~!」
いきなり何を言いやがる。
「ダメダメ、お父さんは仕事してきて疲れてんだから。」
おゆき「やっておやりよ。公園で他の子がカメさん独占してて乗れなかったんだよ、元ちゃん。」
「1かいらけ!1かいらけ、おねがい!」
手を合わせる幼な子。
「俺と同じじゃねえか。やれやれ…」
観念して畳に跪こうとした時、
「ほら元ちゃん、お馬さんだよ。」
ドロロン!お紺がメリーゴーランドの白馬に化けてくれた。元は目を輝かせて馬に乗った。キャッキャ言って喜んでいる。お紺も良いとこあるじゃねえか。
「いいな~元。次、お父さんにもさせて。」
これは、子供の機嫌を取るよくあるリップサービスではなく、率直に羨ましくて出た本音である。
ひとしきり玄関~居間をパッパカ跳ね回ってもらい満足した元は馬を下りた。さあ俺の番だ。しかし、
「あ~疲れた!もうダメ。」
お紺が狐に戻ってしまった。
「あ!俺まだだぞ!元の次って約束したんだから。」
「そんなの元ちゃんと約束したんでしょ。あたい知らないもんね。」
「そう言わずにさ~、お願い1回だけ。」
「しょうがないなあ、それじゃあワンランク落ちるけどそれで構わない?」
「結構です。よろしくお願いします。」
 俺は狐に跨った。ドロロン!お紺が化けたのは、首から下がただの棒になっているおもちゃの馬だった。こんなんだったら魔女の箒か何かの方がまだましだ。
俺は狐に跨った。ドロロン!お紺が化けたのは、首から下がただの棒になっているおもちゃの馬だった。こんなんだったら魔女の箒か何かの方がまだましだ。とはいえ、俺には何の益もなかったものの、お紺の化け技は元に対しては平和利用できたことは確かだ。
完(2016.5.5)