第一章
昨年の12月、俺はアラスカ・フェアバンクスに飛んだ。前々から一度はオーロラを見たいと思っていたところ、前話のスロヴェニア旅行の際、レストランで隣り合わせた日本人のご婦人から、この冬がオーロラが頻発する最後のチャンスらしいと聞いてからは、是非とも行かねばならないという気概が生まれた。調べてみると、太陽の活動との関係でオーロラの最後のチャンスだという噂は巷に相当流布しているらしく、各旅行会社もオーロラ観光に力を入れていた。
「せっかく行っても必ず見れるとは限らない」と二の足を踏むような鬼便的思考回路は持ち合わせない。俺様が出向くからにはオーロラが現れないはずはないのだ、という根拠のない自信が私にはありました。俺は珍ツリの海外旅行ブランド「ハラダイ」の商品、カナダのイエローナイフのオーロラツアーに申し込んだ。オーロラとナイアガラの滝観光がセットになっていてお得だと思った。(パンフの企画の中には、オーロラとハワイ旅行のセットもあったが、何考えてんだか分からない。)
ところが、超人気で既にキャンセル待ちの状態だった。あの噂は旅行好き達のみならず、流行を追うミーハーな大衆どもに蔓延しているものと見た。まあ俺自身も噂に踊らされているには違いないが。とにかくキャンセルが出るのを待つしかない。
ある日、珍ツリの営業マンから連絡が入った。キャンセルの見込みはないという。ただ、オーロラのみを目的にするならアラスカのツアーに空きがあると案内してくれた。穴埋めに使われたら営業マンをぶっ飛ばそうと思うが、意味ある内容と値段なら考えないでもない。パンフをもらって検討することにした。茶の間の炬燵でパンフを広げた。
「ふむふむ、旅行会社共同のチャーター便だから直行便か。こりゃいいや…。げ〜!クリスマスは商店が軒並み閉まるから日本から食糧持ってかなきゃならないんだって!」
マリアが横からパンフを覗き込み「ホテルノリストランテハ?」
「24、25日は駄目みたい。オーロラ鑑賞は夜中だから、朝飯もつかないんだとよ。」
「ソレワツマラナイダワ。アラスカデ、ワザワザカップ麺食ベナサイト言ウノデスカ。」
「カップ麺はかさばるよ…。けど柿ピーとかゴマ煎餅とかで暮らすなんて貧相すぎるよなあ…。そうだ!酒はどうすんだ?どうしてくれるってんだ?」
元が口を挟んだ。「オシェンベ食ベユ!」
「おっと?店が閉まる前日に大型スーパーにお連れしますだってよ。」
「ソシタラ、プロシュットトカ、パーネ買エルワ。」
「パンパン食ベユ!」
「お前は食うことばっかだな。鬼便おじさんみたいだぞ。」
「ヒドイワワカダンチャン、アンナ太カ人ト一緒バシテ。」
「何で博多弁?」「テレビデ覚エタバイ。」
その時、雪女のステファニーが店から帰ってきた。カナダに行く話をした時は、彼女の先祖がカナディアンロッキーの雪だから、現地の親戚によろしく伝えて欲しいと頼まれていた。この分では約束は果たせない。
「只今帰りました。」と茶の間の前で三つ指ついてお辞儀をする。
「俺、アラスカに行くことになりそうだ。約束してたけどカナダじゃなくなっちゃった。」
「そうなのですか。アラスカの何処でせうか?」
「えーっとね」パンフの文字を確認し「フェアバンクス」
「フェアバンクス?!その旅行、私もご一緒させて頂けませんでせうか。」
「やっぱ親戚でもいるのか?」
「親戚どころか直系の曾お祖父さんがエスキモーの一員としてフェアバンクス近郊で暮らしてござります。齢参千五百歳ですがまだまだ現役で、山の中で犬を育て、犬ぞり屋を営み居り候。」
「犬ぞりもいいな。乗せてもらえるかな。」
「もちろんにござりまする。お祖父さんにとっては曾孫のご主人様一家ですから。」
「おい元、犬ぞり乗れるぞ。ハスキー犬が引っ張るんだ。楽しいぞぅ。」
「ワンワン!ワンワン乗ユ!」
俺の脳裏には雪の照り返しの中を疾走する親子が思い浮かんだが、元の心には、マル(※第42話参照)のような秋田犬に跨り春のお花畑を突っ走る自分が思い浮かんだかも知れない。果たして間主観性は基礎づけられるものなのだろうか。この際どっちでもいいが。
ともかく、初めての地に知り合いがいるのは心強い。貧相な飯の心配もしなくて済むかも知れない。でもステファニーは妖怪だからパスポートが取れない。となるとツアーに申し込むこともできない。
「なあステファニー、どうやって行く?バリ島の時(※第39話参照)みたいに島づたいに渡るか?」
「はい。冬ともなれば雪が積もりますので、北海道から北方四島、カムチャツカ半島、アリューシャン列島と悠々渡って行かれまする。雪さえあれば雪女は無敵。南国に渡るより楽チンでござる。」
環太平洋は雪女の移動には便利にできているようだ。
「シロクマに食われないように気をつけろよ。それにしても雪女のお祖父さんって雪男?」
「あに図らんや、雪女です。魔女といっても男もいる由にて。男の雪女も在り居り侍りいまそかり。」
* * * * * * * * * *
出発が近づいてきた。俺たちの渡航日の1週間前、西高東低の気圧配置の日に雪女は旅立った。俺はオーロラ撮影用に三脚を買ったり、デジカメの露出時間を勉強したり、防寒のためのウィスキーを入れる平たい金属製ボトルを探したりと、旅行の準備をした。マリアは一家の防寒着を買い揃えた。
ところがいよいよ出発という前日に元が風邪引いて熱出してしまった。旅行どころじゃない、すぐに医者に連れて行った。いつもの番町総合病院。
青山先生「まあ普通の感冒だね。インフルエンザじゃないから心配ない。」
「本当か?絶対?もしや重い病気じゃ…」
「大丈夫だっちゅうの!私が天才医師ブラックジャンクのモデルだってこと忘れたんじゃあるまいね。」
心配ないと言われてホッとした途端、旅行が気になり始めた。
「良かった…。今日治りますかね?」
「馬鹿言っちゃいかんよ君。二三日は安静にさせとかないと。」
「だって明日からアラスカ行くんだよ!犬ぞり乗せるんだから。天才なら治せ、この爺い!ヒグマの餌食になりてえか!」
「お前さん、息子が大事じゃないのかい?こんなちいちゃな子、風邪引いて極地行って
「何だとこん畜生…」熱で苦しんでる子を置いて旅行なんか行ける訳ゃねえ。「…でもすいませんでした。」
アラスカは諦めるしかないか。直前だとキャンセル料は全額だろうなぁ。けどしょうがねえや。おっと、先発させたステファニーに連絡しなきゃ。奴は確か携帯持って出たな。予定ではもうアラスカ本土に到着しているはずだから、アンテナ基地もあるだろう。
「そうですね。それでは致し方ござりませんね。」
「お前一人だけど、せっかくだから楽しんで来なよ。お祖父さんによろしくな。」
続く(2013.3.3)
第二章
とはいうものの、俺はアラスカが諦めきれない。キャンセル料はどうせ全額だ。成田出発は夜10時だし、ぎりぎりまで払う気になれなかった。元がピョコンと飛び起きて全快バリバリだよお父っつあん、Let's go! Arctic! なんて言い出してくれるのではないかと、ほのかな期待をかけていた。
だが、そうそううまくは行かない。たとえ『若旦ちゃん』の作者であっても、人の身体だけはご都合主義で描く訳にはいかない。超人一家の物語ではないのだ。
(※瀕死の大怪我しても翌日には平気で敵と戦う漫画があったりするが、『若旦ちゃん』はそうではない。事実、俺は指をコピー用紙で切っただけでとっても痛がる男である。)
お粥を食べる息子を眺めながら、その年は暮れていった。
と思いきや、珍ツリの営業マンが電話してきて、次のツアーに空席ができましたと言うじゃないか。ありがとう小枝芽クン(※営業マンの名前)、是非参加させて頂きます!ということになり、俺は直ちに旅支度を調えた。ただし空席は一つだけ。子供はもうピンピンしているが、席が一つじゃ母親が付き添えないからしょうがない。俺一人で元を海外に連れて行く能力はない。だから申し訳なかったが、マリアにだけ事情を話し、ごねられると面倒なので、元が寝ちまうのを待って成田に向かったのだった。俺って嫌な奴。
* * * * * * * * * *
フェアバンクスの空港に到着すると化け狐のお紺まで来ていた。ご存知の通りステファニーとお紺は仲良しだ。聞けば、俺が行けなくなった時に、寂しくなったステファニーがお紺を誘い、お紺は神楽坂のお稲荷さんからサンフランシスコの日本人コミュニティに鎮座する稲荷社へと瞬間移動し、そこから鉄道の屋根を乗り継いでアラスカへ入ったのだった。そういえばここ数日お紺の姿を見ていなかったな。お紺はパーカの小娘姿だった。
「外はマイナス39℃だよ。」
「えー?!全然想像つかねえんだけど。俺、煙草吸いに行っていいかな?」
「試しに出てみれば?どんなもんか。」
飛行機内の禁煙には慣れたが、やはり地上に降りたら一服を満喫したい。俺は晴れた朝方の外に出た。
 時刻は午前11:30だったが、冬のアラスカは日の出が11時だから日差しは地平線から差し込み、朝の風情なのである。キーンと冷たい空気が顔と首の皮膚を刺す。革と毛糸の手袋を取り、煙草を内ポケットから出して火を点けた。ふ〜っ…と息を吐く。美味いことは美味いが、やたらと寒くて煙草を持つ指がかじかんでしまうので、早々に屋内に戻った。何しろ、素手の掌から湯上がりの如く湯気がもうもうと立ち上るほど、寒さが体温を奪うんだから。
時刻は午前11:30だったが、冬のアラスカは日の出が11時だから日差しは地平線から差し込み、朝の風情なのである。キーンと冷たい空気が顔と首の皮膚を刺す。革と毛糸の手袋を取り、煙草を内ポケットから出して火を点けた。ふ〜っ…と息を吐く。美味いことは美味いが、やたらと寒くて煙草を持つ指がかじかんでしまうので、早々に屋内に戻った。何しろ、素手の掌から湯上がりの如く湯気がもうもうと立ち上るほど、寒さが体温を奪うんだから。「どうだった?」「いやあ、冷たいっていうより痛みだね。お前よく平気だね。」
「だって本物の毛皮生えてるからね。」
「冬のアラスカにては、深呼吸するのは御法度なのですよ。肺が凍るから。学校では子供達に冬は走らぬやう教育している由にござります。」
「えっ?早く言ってくれよ!俺、思いっきり深呼吸しちゃったじゃねえか!しかもニコチンとタール入りでよぅ!知らないから冷気が気持ちいいと思っちゃったじゃねえか!」(3.11)
とか何とかお紺たちとガヤガヤやっていると、到着ゲートから出てきた夫婦者の男が話しかけてきた。「いいですなあ、こちらにお知り合いがいらして。」
いきなり話しかけるなんて機内で俺のことを見かけてたのかな?こっちは知らねえなあ。オーロラツアーの同行者だろうか。どことなく地位のありそうな社長っぽい雰囲気だ。
「お知り合いなんて上等なもんじゃないんです。家族っていうか飼い犬っていうか…」
「は?」おっといけねえ、化け狐をばらしちゃまずい。
「いや違った。今、煙草吸ってクラクラしてましてうっかり。留学中の親戚の娘なんで。」
「近くで煙草吸えるんですか?」とパイプを懐から取り出した。
「ええ、そこのドア出たすぐの所に灰皿がありますよ。」
俺がガラス窓の外を指さすと、男は嬉しそうにドアを出て行った。
「気ぃつけた方がいいっすよ〜!肺が凍るからね。」と声をかけたら、奥さんが、
「まあ!そうなの?!大変!あーた!ああたぁ〜!」と夫の後を追った。言葉遣いからして社長夫人ってとこだな。
「尾形担当のハラダイツアーの皆さん、お集まり下さ〜い!」添乗員が一同を招集した。この男とは成田のカウンターで挨拶したが、デブ禿でしかもオカマっぽい指使いをする、俺の嫌いなタイプだ。「尾形」という、字は違うが同姓だから余計に嫌だ。
一行は総勢14人位だった。「位」というのは、俺には関係ない人達だからだ。その中には先程の社長夫妻もいた。この人は悪い人じゃなさそうだ。中年女の二人組は旅慣れた態度が鼻につく。若い夫婦が二組いるが、個性がないから最後まで顔を覚えられなかった。あと4人家族の親子連れ。その他いろいろ。(3.12)
* * * * * * * * * *
さて、パッケージツアーなので狐と雪女とはひとまず別れ、先述の人々とともに団体旅行が始まった。バスで市内をぐるぐる移動し、お昼に最北のビール醸造所で巨大ハンバーガーを食べ、アラスカ石油パイプラインとアラスカ大学の博物館を見学し、夕飯に銀鮭のグリルをいただいた。お仕着せの観光コースだ。
集団行動は苦手だが社会性がない訳じゃないから最初のうちは我慢してたが、添乗員があんまりひどいので俺はツアーを離れることにした。尾形は観光案内は現地ガイドに丸投げし、自分は食事時だけ出しゃばって、USAの食べ物は不味いという偏見を、現地の店員が日本語を解さないのを良いことに客の前で面白おかしく吹聴した。だが、面白くもおかしくもなかった。
「焼きすぎるんですね、こっちの人は。日本人はもっと繊細な焼き加減が好きですから。」
「この鮭は、本当は美味しいんですよ!ソースさえ甘くなければ。ほ・ん・と・うは!」
「店では《日本人は醤油がありゃ何でも良いんだろう》と、ちゃんとテーブルに用意してくれてます。」
などと、添乗員の自分は事情通だと誇示したいのか無節操にわめき散らしていた。調子合わせて笑ってしまう日本人も軽蔑した。俺は「この肉だって好きですよ」と言って尾形に逆らった。だって真面目にウェルダンの肉が好きなんだし。
それと、仕事柄DELTA航空のマイレージが溜まっちゃって困るんだと自慢した。自腹で出張する訳じゃあるまいし、それは客の金だろう。それから、俺がアメリカ人と話そうとしたら「英語の得意な人はご自分で交渉して下さい。」とわざと他の客に指示をした。
こんなバカに引き回されるのなんか御免だ。やってらんねえやと思った俺は、初日のホテルはフェアバンクス市街の大型ホテルだったが、何食わぬ顔でチェックインした後、ひそかに妖怪どもと落ち合い、ステファニーの曾爺さんの所に連れてってもらった。(3.13)
山の中までは雪女の運転するワゴン車で行った。ステファニーは運転ができる。島政の軽トラックで技術をマスターしたのだ。無論無免許だが、そもそも戸籍も住民票もなく、いわんや人体でもない雪女には法律は無力だ。車は曾爺さんの物だそうだ。
「でも右側通行なのには困りました。」
「まあそうだろうね……え?あ!!ちょい待て!」
いきなり道路脇の白樺の間からムース(ヘラジカ)がのっそり現れた。キキーーーーーーッ!!
極端に日の短いアラスカでは夕方は真っ暗だから、見通しが悪いのです。助手席にいたお紺が窓を開け《獣語》でギャンギャンと怒鳴った。ムースは気のせいかせせら笑うように、我が友茄子クンの如き大きな鼻の穴から水蒸気を吹かして立ち去っていった。
「何を話したんだ?」
「別にぃ。…田舎者めが、ボヤボヤしてたらこのお紺ちゃんが食っちゃうぞ!って。」
「今の鼻息から察するに、ナメられたな田舎者に。」
お紺、唇とんがらして「ふんだ!若旦ちゃんもまだまだ野生動物のことは無知だね。」
「何を?!どうせ図星だから悔しくてそんなアヒル顔してんじゃねえのか?アヒル顔の狐って誰の真似だい?」
「アヒルじゃなくてふくれてんの!!じゃあ聞くけどさ。あたいがここに来るまでに、どんな殺戮してきたか知ってんの?」
「知らない。」「ある時は街角の鼠を俊敏に捕らえ、またある時はスーパーで卵を電光石火で掠奪し、はたまたある時は番犬のドッグフードを無慈悲にも接収し、しからずんば…」
「わかったわかった。じゃあ今追い払った動物は何て言うでしょう?」
「ト、トナカイ…」
「お生憎様、ヘラジカだよヘラジカ!無知だね〜。無知を知れ!それが真の知へのスタートなんだからな。」(※『ソクラテスの弁明』参照)
ステファニーが話題を転じ仲裁に入った。「ほら、そこが曾お祖父さんの家です。」
暗がりの中にぽつんとオレンジの灯が灯り、ログハウスが建っている。奥は針葉樹の森が続いているようだ。犬を育ててるってことだが、正面からは見えないから森の中に犬舎があるのかも知れない。車は家へと続く小径に入る。
「でさ、お祖父さんは何ていう名前?」
「申し遅れました。ティブッチョと申します。」「でぶっちょ?」
「いえティブッチョ。曾お祖父さんの祖先は、ペニンアルプスはモンテローザの氷河なのです。」
「なるほど。で、本当にデブッチョなのかい?」
「本当も何も…。まあ、お会い頂ければすぐにお分かりになりますでしょう。」
三人が車を降りると、突然、暗闇から二十頭前後のハスキー犬が飛び出してきた。「うわ!」俺は仰け反った。
隣にいたお紺が「キャーーーーーッ!!」と叫んで逃げ出した。キャンキャン鳴きながら、追う犬とともに林の中へ消えた。
後ろから太い声がした。“あの娘、さては狐だな。”お祖父さんだと思って振り返ると、巨大な熊のシルエットが目に入った。「うわ!」また仰け反った。
続く(2013.3.14)
第三章
 “ようこそ!アラスカへ”熊が英語で手を差し伸べてきた。目を凝らすと、頭から後ろ足までの熊の全身毛皮を被った老人であった。背丈は2mを越えかなりの体格だが、デブではなかった。俺は顔を見上げながら握手に応じた。
“ようこそ!アラスカへ”熊が英語で手を差し伸べてきた。目を凝らすと、頭から後ろ足までの熊の全身毛皮を被った老人であった。背丈は2mを越えかなりの体格だが、デブではなかった。俺は顔を見上げながら握手に応じた。“緒方といいます。どうぞよろしく。”
“曾孫がお世話になり、サンキューベリマッチ。私はティブッチョです。”
小屋に案内された。このクソ寒いのに屋内に火の気配はなかった。雪女の住居だから当然ではあるが、生身の人間様には過酷な環境だ。実は、薪をくべた暖炉の前で温かいスープか何かで歓待される、シチューのCMみたいなイメージを抱いていたのだが、幻想に過ぎなかった。しかも、室内に入り毛皮を脱いだ老人は高さ50cm位の
“チビだとナメられるもんだで。アメリカ人はでっけえからのう。”
“ふ〜ん。雪女は登山者を驚かすのが仕事ですからねえ。”
“んだ。名前からも分かるとおり、わしはイタリア系でね。苦労しましたわい。”
余談だが、英語に田舎訛りがあるのは、日本語に翻訳する際の技術である。西部劇の吹き替え版を見てみてください。
“おーい!エレオノーラ!”老人が奥の部屋に声をかけた。
“今行くわー!”と答えて出てきたのは、今度こそデブッチョの、黄色人種の厚化粧の女であった。眼が線のように細く、どこを見ているんだか読み取れない。
“ハーイ!どこから来たの?”
“東京ジャパン”
“それはそれはようこそ。私エスキモーなの。”
“あの…この人、雪女じゃないんで?”
“彼女は人間だども。赤ん坊の時、狼にエスキモーの村からさらわれてのう。わしが育ててやっただよ。エレオノーラに食事の支度をさせておるだで、さあ奥へどうぞ。”
テーブルには人間らしい食べ物が用意されてあったので、俺はホッとした。山盛りのフレンチフライにハンバーグ、ローストチキン、トマトにレタスにベーコンいわゆるB.L.Tと、典型的なアメリカンな食卓である。これを毎日炭酸飲料と一緒に食ってたら太るに決まっている。このエスキモー女も、アメリカナイズされてしまいこんな姿になったのだろう。猟で獲ったアザラシを食ってれば良かったものを。
ところでお紺はどうしたろう。奴は化け物だが哺乳類には違いないから、雪だけ食って過ごすことはできない。生肉とはいかないがこの食事でも必要なエネルギーは摂れる。あいつにも食わせてやりたいなと思った。ステファニーに「お紺は帰ってきた?」と聞いた。
「いえ、未だ戻りませぬ。」
“さっきの狐娘のことかね?それなら心配要らん。わしの犬たちが歓迎してくれとるじゃろうて。日本の狐は珍しいからのう。”
* * * * * * * * * *
たらふく頂き、世界最北の醸造所から取り寄せた地ビールなども嗜んでいたら、すっかり夜が更けた。ぼちぼちオーロラ鑑賞の時間だ。ツアー客達の向かう鑑賞スポットに、俺は犬ぞりで連れて行ってもらうことになった。添乗員の尾形には、一人で行くからと電話で伝えた。
外へ出ると、正体の獣の姿のままのお紺が駆け寄ってきた。
「あたい、この犬たちの親分になっちゃった。へへへ」
「いきなり親分かよ。」「うん、だって相手はただの犬だしさ。知恵が違うのよ知恵が。」
「まあ統率されるのが習性だろうからな。」「このお紺ちゃんを見直した?」
「いや別に。犬畜生の上下関係なんて興味ないもんね。」
「あ〜、そんなこと言うと子分に命じて食い殺しちゃうんだから。」
牙をひん剥いて威嚇する狐。だが眼は笑っている。昔から『江戸っ子は五月の鯉の吹き流し、口先ばかりで
「うそうそ。そう怒るなよ。ひとっ走り俺様をオーロラロッジまでお届けしてくんねえ。ほら、これあげるからさ。」(3.23)
俺はエレオノーラからもらった未調理の鶏の腿を茶袋から出し、空中に放り投げた。お紺は目を輝かせて素早く飛びついた。
* * * * * * * * * *
太っちょエスキモー女の運転するスノーモービルを先導として、犬ぞりは疾走する。再び大男となったティブッチョ爺さんがそりの舵を取る。お紺は犬集団の先頭で親分として頑張っている。そりの客席には俺とステファニーが乗った。俺が前だ。
 スキーウエアや毛糸のセーターを着込んでいるが、背中に雪女がしがみついているので真に寒い。しかも、走り出してすぐに呼気の水蒸気が眼鏡を曇らせる。急いで拭こうとしたらガチガチに凍っていて何ともできない。マイナス数十℃の大気を時速20km超で切り裂いて行くのだ。眼鏡が凍るのも当たり前だ。でもこれでは視界が真っ白でせっかくの疾走感を味わえない。仕方なく眼鏡をズリ下ろしたみっともない面相で前進した。爽快というよりも修行だった。
スキーウエアや毛糸のセーターを着込んでいるが、背中に雪女がしがみついているので真に寒い。しかも、走り出してすぐに呼気の水蒸気が眼鏡を曇らせる。急いで拭こうとしたらガチガチに凍っていて何ともできない。マイナス数十℃の大気を時速20km超で切り裂いて行くのだ。眼鏡が凍るのも当たり前だ。でもこれでは視界が真っ白でせっかくの疾走感を味わえない。仕方なく眼鏡をズリ下ろしたみっともない面相で前進した。爽快というよりも修行だった。30分ほど走ってロッジに到着した。爺さん達に礼を言って別れ、ドアを開けると尾形が椅子に座った客達に演説をぶっていた。
「オーロラが一番出やすい時間帯が大体10時半から2時くらいなんです。ですから今ここにお連れしている訳ですが、予め申しておきますが毎日見れるとは限りませんからね。旅行中一回も出なかったツアーもあります。そんな時は帰りの飛行機が暗いんですね〜、雰囲気がね〜。ハハハハ!」
このバカ野郎、客の不安を煽ってそれでも業者か。
「いや、今日は出ますよ。」俺は演説会に割って入った。
「ああ緒方さん。あんまり勝手な行動してもらっちゃ困りますね、ツアーなんですから。他のお客さんの迷惑も考えて下さい。」
「それはごめんなさい。でも今日は出るんだから。間違いないって。」
「何の根拠があって。太陽観測の気象情報では、盛んになるのは二三日後ですがね。」
「天気予報ほど当たらない科学はないじゃねえか。俺がはるばる日本から来たからには出るものと決まってんだ。今日は出ます!」
「あーそうですか。そうなると良いですな。出れば私も安心だ。フフン」
尾形は嘲笑した。他の客も、身勝手な男よりも下らない添乗員を信頼しているようで、白けていた。だが俺の野性の勘は、今夜は出る、明日は出ないかも知れないが、初日の今夜は必ず出る、と告げていた。(3.24)
* * * * * * * * * *
午後10時、各自雪原の好みの位置に三脚を立て、観測が始まった。酷寒なので、外に出て空を見上げたり、小屋に戻って暖を取ったりを小刻みに繰り返しつつ、オーロラ出現を待った。
二時間近く経つともうくたびれてきた。テーブルの前で腕組みしてじっとしていた。心の中では「やっぱり今日は出ないのかな。俺の勘って何だったのだろう」と悶々としていた。時折、客がモニター画面を見ながら、「あれオーロラじゃない?」とか言う。ここのロッジは高感度カメラを北の空へ向けてモニター観測しているという便利な所だった。だが尾形は「あれは雲ですよ」オーロラの出始めは雲と見分けがつきにくいらしい。「皆さん、だんだん何でもオーロラに見えてくるんですな。ハハハハハ」
どこまで客を見下すつもりなのかね、この
「あれ?あれ違う?!」
俺は見るが早いかオーロラであることを直感し「そうですよ!」と、俺に話しかけた訳でもないのに答えた。「出た!」と小声で口走りつつミトンの手袋とデジカメをふん掴み、外に飛び出した。
見上げる北の空にぼんやり浮かぶ白い雲霞。その長細い塊は長さを増し、横に棚引き始め、徐々に色を増して薄いレモン色を帯びてきた。すごい!本物のオーロラだ!俺に続いて外に出たロッジの人々が歓声を上げた。棚引きが上へ下へ、西から東へと風を孕むカーテンのようにうねり始めた。
小一時間ほど人間の目を楽しませ、やがてオーロラは消えていった。大満足だぜ。あまりに夢中で左手の小指が凍傷寸前になった。
続く(2013.3.27)
第四章
オーロラさえ見えればオーロラツアーは本望である。翌日、これまた俺の勘どおりオーロラは出なかったが、一行は余裕で「まあ今日のところはいいでしょう」みたいな、水戸黄門のような寛大な態度だった。無責任な尾形も実はプレッシャーがあったらしく、前に比べれば落ち着いた表情をしていた。俺もこの禿バカを許す気になっていた。
さて滞在三日目からは郊外のチナ・ホットスプリングスという温泉リゾートに泊まり、近くの丘からオーロラを見る予定だ。観光バスで現地へ向かう。今回はステファニーたちもそこに宿を取っている。人気のホテルだが、地元のティブッチョ爺さんの手配でうまく予約が取れたのだ。向こうで落ち合って楽しくやろう。
宿に関するスタッフからの一通りの説明を聞き、鍵をもらって自室に入った。103ロッジの6号室だった。俺はいわゆる「お一人様」だから、ツインベッドを独り占めだ。でももったいないので、内緒でステファニーを泊めることにした。爺さんが取れた部屋は二人部屋一室だけだったから人数的に足らなかったし、エレオノーラは人間の女だから万が一間違いがあってはいけない。となれば、雪女と泊まるのが最善だろう。お紺という選択肢もあるが、奴はすっかり野性に目覚めてしまい、野山を駆け巡っていて一所に落ち着こうとしない。その点ステファニーは大和撫子で、人間の常温にも慣れてるから、俺のホテルライフも快適になりそうじゃないか。ステファニーの方も嬉しそうで、いそいそとコーヒー沸かしたりしている。
「おう、ステファニー。ひとっ風呂浴びて来らぁ。」「いってらっしゃいませ。」
俺はホテルの露天風呂に出かけた。103ロッジを出て雪道を温泉施設まで歩く。圧雪された新雪をキャンピングブーツが踏むキュッキュッという踏み音が心地よい。アラスカは寒すぎるので、降った後何日経っても新雪のままなのでした。コインロッカーに着ぶくれの衣服を詰め込んで、海パンになって風呂に向かった。欧米の浴場は素っ裸では入れないのが残念だ。開放感というものが皆無だ。
(※そういえば、コインロッカーに必要な25¢玉をクォーターと言うが、1$紙幣をクォーターに両替したい時の表現を、テネシー出身日本在住のアメリカ人から“I need quarters for the coin locker.”と教わって現地で使ったら、“Coin?”と聞き返された。日本の観光客が使うのが旅慣れぶっていて変なのか、テネシーとアラスカの違いなのか。出鱈目を教わったはずはないのだが…)
外に続くドアを開けると氷点下20℃の寒気が襲う。これでも今日は暖かい方だ。でも裸だから縮み上がりそうに寒くて、うっかりバスタオルを持ってきてしまった。畳んだバスタオルをアフリカの水汲みのように頭に乗せたまま、俺は風呂へと進んだ。露天風呂は水深約1.2m。日本と比べるとまるでプールだ。坐ったり寝そべったりして身体をほぐすというセンスはないらしい。濡れていない岩にタオルを乗せて、突っ立ったまま温まった。
風呂の真ん中でロシア人がはしゃいでジャバジャバやっているのを尻目に、俺は端っこの岩壁に背中をもたれながらじっくりと温まった。じっと動かず、頭皮から汗がにじみ出てくるまで肩まで浸かる。これが正調、温泉の入浴法というものでしょう。ただ、手で湯をすくい顔を濯ぎフーと思って髪をかき上げると、アラスカ仕様に伸ばしていた髪の毛が凍っていたのにはビックリした。たとえ雪国でも日本の冬の露天風呂ではあり得ない。
そろそろ上がろうかなと思った時、目の前にステファニーが湯の中からぬっと首を出した。混浴だから構わないのだが、いきなりだと誰だって驚く。彼女は水辺の瞬間移動を身につけていたんだった。(※第35話参照)「わっ!何なんだ?!」
「お風呂の後はご夕食になさいますか?それともお休みになられますか?」
周りの客がこっちを見ている。誤解されそう。
「え?こんなところで聞くなよ。あーーっ!驚いたからタオルを落としちゃった!」
「相済みませぬ。直ちに取って返し、代わりの手拭いをば!」
「ま、待て待て!」水中に没しようとする雪女の肩を掴み引き留めた。「皆が見てるとこでお前が潜って浮かんでこなかったら、それこそ大騒ぎだ。この濡れタオルで良いよもう。」
「お離しくだされ!ご主人様のお命に関わっては一大事!何としてでも乾いた手拭いなりおしぼりなりとも…」
「だから大丈夫だから!」「お離しくだされ!武士の情け!おのれ上野介〜!!」(3.24)
お約束通り羽交い締めにしようとしたが相手は雪の精、力を込めたらスッと腕を透り抜け湯の中に消えてしまった。どうしようと思って周囲を見たら、折からの寒風でもうもうと湯煙が渦巻いて視界不良だったため、大和撫子の失踪は他人に気づかれずに済んだ。
とまあちょっとしたハプニングはあったが、アラスカで露天風呂に入れるのは極楽だった。普段海外旅行の時はシャワーで済ませるのが当たり前だと思っているから、たとえ立ちん坊でも、思いがけず熱く深い湯に浸かれるのは風呂好きの日本人には嬉しいものなのです。(おっとそうだ!出雲の玉造温泉にもこんな馬鹿でかくて深い混浴風呂があったっけ。あれはなぜか有り難くなかった。)
出入口へと続くスロープの浅瀬に上がり、凍った濡れタオルで身体を拭いたら寒かった。(3.27)
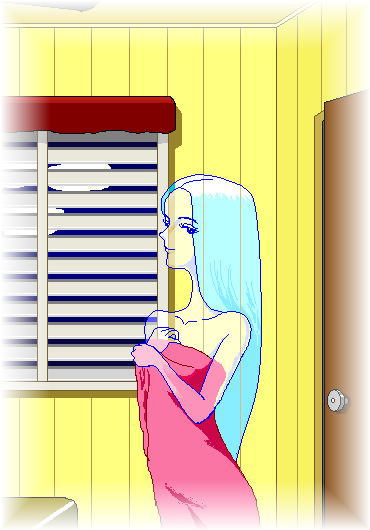 部屋に戻った。ステファニーの姿はない。行き違いになったかな、とぼんやり突っ立っていると、バスルームから半透明のステファニーが現れた。
部屋に戻った。ステファニーの姿はない。行き違いになったかな、とぼんやり突っ立っていると、バスルームから半透明のステファニーが現れた。「どうしちゃったんだ?その有様は。まるでお化けだぞ。もっとも
「この部屋、たいそう乾燥しておりまして…」
この雪女は厳しい修行の末、高温には耐えられるようになったのだが、何といっても雪の精、未だに乾燥には弱いのだ。アラスカは雪深いわりに乾燥が激しい。寒い分だけ室内はガンガン暖房を焚く。人間の俺でさえ、服を脱ぐ時の静電気には困らされたものだ。上着を脱いでるのに素肌までビリビリッと感電するんだから。ステファニーは乾燥しすぎて透明人間になっちゃったので、シャワーを浴びて水分補給していたのである。
結局、ステファニーも屋外で寝泊まりすることになり、俺は孤独なホテルライフを過ごすことになった。
続く(2013.4.3)
第五章
さて、滞在四日目、オーロラ鑑賞の最後のチャンスだ。この日もまた俺の野性の勘がオーロラ出現を予告していた。だからツアーのみんなに言いふらした。氷の博物館内のバーで隣り合わせた母娘にも「今夜は出るから丘に行く雪上車に申し込んだ方がいいよ」とお勧めしたりした。で、実際にちゃんと綺麗なのが出たから大したもんだ。(本当に俺の勘が冴えていたのかどうかは分からない。でも要は出るか出ないか丁半勝負、季節自体はオーロラシーズン、出ると思っていた方が幸福を呼ぶのではないだろうか。)
昨日丘の上まで雪上車に乗ったが、恐ろしくガタガタ揺れて乗り心地は最低だった。しかも急勾配を行くから、横の人に体重をかけてはいけないと思って踏ん張るから、筋肉痛になった。もう嫌なので、今夜はステファニーにおぶさって丘までひとっ飛びしてもらうことにした。
その頃は満月だったので、月明かりを頼りに空を飛んだ。(4.3)
「おんぶの身で言いにくいけど、あんまり本気で飛ぶなよ。お前が本気出したら吹雪になっちまう。」
「ご心配なく。ただでさえ上空は気温が低うござります。ローギアで参りましょう。私が若旦ちゃんを危険な目に遭わすはずもござりませぬ。」
「お手柔らかに頼みます。」
それでもビュビュビュビュビュビュ〜ン!と空を飛ぶ。
「さぶい…」ステファニーの雪見大福のような身体にしがみつく。もっと寒い。
「少しはご辛抱下さりませ。あんまりのろいと落っこちてしまいまする。」
「うぇ?…よ…妖怪でもそういう物理的な法則に…?」歯がカタカタ鳴る。
「いえ物理的に重いのはあなた様。」
俺はいきなりしゃっきりした。「おいおい、俺は江戸っ子だい!華奢で小柄と相場が決まってんだ!デブ呼ばわりはよしてもらおうじゃねえか!」
「失礼つかまつった。寒ければ一旦降りましょうか?」
「誰が降ろしてくれっつった?俺は重かぁねえと言いてえんだ!」
「待って!」
「いや待てねえ!」「違うの」「いや違わねえ!」「何が?」「何だっけ?」
「だから違うの!ほら見て!下にお紺ちゃんが!」
雪女の肩越しに下を見やると、林の間を駆け抜ける小さな獣の影。
「あの表六玉め、何やってやんでえ。さんざ心配かけやがって。お〜い!」
「待って!」「何だよ、今度は何が違うんだ?」
「お紺ちゃん、他の動物と一緒みたい。」「え?」
よく見ると、お紺と同じくらいの小動物の影がお紺を抜いたり戻ったりしている。
「狼に襲われているんじゃねえか?満月だし。」「いえ、私には狐に見えまする。」
ステファニーは緊急着陸し、俺たちはお紺の後を追った。足跡発見。
「おー、こりゃ確かに狐の足跡だ。二匹でじゃれてるみたいな。」
「ね〜そうでしょう。アラスカの狐と仲良くなったのに相違ござりませぬ。」
「よし見に行こうぜ。」「待って!」「もういいよ、それは。」
「察するにきっと相手は純朴な田舎の狐でありませう。人間がいきなり現れてはお紺ちゃんの初恋も淡雪の如く…」
「じゃあ俺はティブッチョ爺さんの熊の毛皮でけだものに変装しよう。」
「残念ですが、曾お祖父さんは今マッキンリーに吹雪を吹かせに出張中にござります。」
「万金旦?鼻くそ丸めて万金旦?」
「マッキンリーだっての!」「越中富山のマッキンリー?」「もう知らない!!」
そのとき俺は、ホテルのアクティビティーセンターにセイウチの毛皮が飾られていたのを思い出した。(4.4)
ホテルに飛んで帰り、殆どの人がオーロラを見に出ていて無人となっているセンターに入った。壁にセイウチの牙付きの毛皮が飾られている。あれだ。ちょいと拝借しま〜す。I am the walrus! GOO GOO GOO JOOB!
英国風庭園に坐って陽の出るのを待ちたいところだが、そうゆっくりもしてられない。早速毛皮を肩に引っかけて出発した。お紺を目撃した場所まで戻り、足跡を追った。森の奥に進んでいくが、空飛ぶ雪女と一緒でしかも月夜だから遭難する心配はない。うろうろ探索していたら突如視界が開け、森のただ中にぽっかり空いた空間に出た。すると、
「若旦ちゃん、ほら!あれ!」
言われて見上げると、夜空一面、放射状にオーロラが広がっていた。「わぁ〜…すげえ…」これが世に聞くオーロラ爆発ってやつだろうか。
集団でオーロラを見る時は、独り占めにはしない。第一発見者が大きな声で周囲の人達に教えてあげるのが礼儀である。そもそも黙っていたってそのうち誰かが見つけるから、見つけても黙っている奴は、心の貧しい三太郎でしかないことになる。だが、今は俺一人だけだ。思う存分独り占めで良いのだ。きっと丘の上からも見えていることだろう。
言葉にもならず、しばらく黙ってオーロラを見つめていた。写真撮ることすら忘れてしまっていた。ふと左の視野の端に光を感じた。振り向くと何とステファニーの肌の色が普段の純白ではなくなり七色に光り輝いている。
「どうした?」「私にも何が何だか…。オーロラのプラズマ粒子が働いておるのでせうか?」
「大丈夫か?気持ち悪くないか?」
「大丈夫です…と思います。多分」体は平気なようだが、初めての経験に雪女は困惑した様子だった。
とそこへお紺がひょっこり姿を現した。
「わあ!ステファニーすごいことになってるじゃん!」
七色の光につられて森から出てきたらしい。
「おうお紺。うまくやってんじゃねえか?オスはどこだオスは。」
「失礼ね。ジョージって呼んでよ、ジョージって。」
お紺の背後からこの地に棲息するクロスフォックスが一匹、用心深そうに出てきた。
「ジョージはね、人は化かさないけど立派な狐なのよ。あたい、しばらくこっちで暮らすからよろしくね。生活が軌道に乗ったらそのうち日本に里帰りするからさ。じゃあねー。」
と言い残し、そそくさと森へ消えてしまった。あっけない別れだぜ。まあ、あいつらしくて良いか。
「実は私もお別れの時が近づいて参りました。」「えっ?」
「私はいささかの犯しがあって月世界より地上に
そんな話聞いてないぞ。かぐや姫かよ、会津の雪女じゃなかったのかよ。
「遂に御赦免が下りまして、この月夜の晩いよいよ月へ昇ることと相成り候。この体の変容がお許しの証拠。」(4.6)
「そんな急に…。お前まで行っちまうのかよ。」
ステファニーの七色の光が一層輝きを増した。「嗚呼、もう往かねばなりませぬ。おさらばでござる。若旦ちゃん、長い間お世話になりました。このご恩は生涯忘らるるものではござりませぬ。」
ステファニーの足が雪の大地を離れ、空中に浮かび始めた。「どうかくれぐれもお達者で。お酒は飲み過ぎては体の毒ですよ。ご自愛召され。」
「ま、待ってくれ!嘘だろ?な、な、嘘だろ?」
徐々に空高く昇っていく雪女。「さようなら〜さようなら〜」
「ステファニー!!」俺は手を伸ばした。だが間もなく、光り輝くステファニーはオーロラと見分けがつかなくなってしまった。
行ってしまった。一遍に二人も友達と別れるのは辛いもんだ。俺は世の無常を感じ、墨染めの衣を身に纏い出家した、というのは冗談だ。
 別れを惜しむ間もなく、その時俺は自分が遭難者になってしまっていることに気づいた。やばい。雪女も化け狐もいない今、土地勘もない痩せ男にはこの極北の森を生きて出ることは至難の業だ。セイウチの俺は茫然として空を見上げた。
別れを惜しむ間もなく、その時俺は自分が遭難者になってしまっていることに気づいた。やばい。雪女も化け狐もいない今、土地勘もない痩せ男にはこの極北の森を生きて出ることは至難の業だ。セイウチの俺は茫然として空を見上げた。続く(2013.4.7)
第六章
落ち着け、こういう時こそ落ち着きが肝心だ。俺は防寒着の内ポケットから煙草を取り出し一服した。俺は海外では携帯電話は持たないから連絡は取れない。ここでじっと救助を待つか。天気が悪くならなければ、貼るタイプのカイロを着けてるから一晩くらいなら凍死の心配はない。だが、アクションを起こさなければ埒が明かないとも考えられる。雪上車の通路からはそう離れていないはずだ。一か八か森へ踏み入るか。だが星の位置から東西南北は見当がつくけど、道の方向が分からない。尾形が探しに来てくれるかな。でも俺が単独行動している前提でいるからまず来ないだろうな。帰りの飛行機に間に合わなかったら探し始めるだろう。でもそしたらツアーの人達に迷惑かけるなあ。あっ!まごまごしてたら狼に食われちゃうかも知れない。熊はきっと冬眠中だろうけど、狼は冬の期間中飢えているはずだ。恰好の餌食じゃないかよ。
焦った俺は声を限りに叫んだ。「誰か〜!助けてくれ〜!Help! I need somebody.」叫びは虚しく森へと消えた。仕方ない。とりあえず自分の足跡を逆に辿ってお紺を探し始めた地点まで戻ろう。今よりは多少は人里に近くなるはずだ。
俺は歩き始めた。狼の危険に怯えながら一生懸命歩いた。だがいつまで経っても出発地点に辿り着かない。それどころか元の森の開けに戻ってしまった。疲れた俺は半べそ状態になった。これまでにあったいろいろなことを思い出し、後悔したりしていた。後悔し始めると、やがては「後悔しても始まらない」と反対に積極性が出たりするもので、俺は気を取り直した。畜生、もう一度トライだ。
しかしまた元の場所に戻ってしまう。俺は雪原に坐り込み胡座をかいた。何だかまるで狐に化かされてるみたいだ。
「若旦ちゃん」お紺の声だ。
「おお!お紺!助けに来てくれたのか。ありがとう、ありがとう。」
「どう?あたいの化かしっぷりは。」
「何だと?!」確かにお紺の手が狐の前脚になっている。いたずら成功して得意な時のこいつの癖だ。「じゃあ俺が迷ったのはてめえの仕業かこん畜生!この性悪女狐!」
助かって嬉しいのに、どうも性分でつい喧嘩腰になる。
「短気は損気と申します。左様にすぐ怒るものではござりません。」ステファニーが空から降りてきた。
「ステファニー!お前、月で兎と餅つきしてたんじゃないのか?」
「うふふ」雪女は狐と目を合わせた。「若旦ちゃん、懲りた?」「は?」
 実は、一連の出来事はこの一人と一匹の妖怪が仕組んだいわゆる「ドッキリ」企画なのだった。俺が身勝手にも妻子を放ったらかして一人でアラスカに来ちゃったもんで、マリアから懲らしめるよう指令を受けたらしい。お紺が渡米する時点から作戦は始まっていたのだ。壮大な作戦計画だ。まんまと為して遣られた。でも俺の事を思ってしてくれたんだから、感謝しなくてはならない。ただ痛めつけるだけじゃなく旅行を満喫させてくれた上での制裁という演出も心憎い。
実は、一連の出来事はこの一人と一匹の妖怪が仕組んだいわゆる「ドッキリ」企画なのだった。俺が身勝手にも妻子を放ったらかして一人でアラスカに来ちゃったもんで、マリアから懲らしめるよう指令を受けたらしい。お紺が渡米する時点から作戦は始まっていたのだ。壮大な作戦計画だ。まんまと為して遣られた。でも俺の事を思ってしてくれたんだから、感謝しなくてはならない。ただ痛めつけるだけじゃなく旅行を満喫させてくれた上での制裁という演出も心憎い。「いや思い知りました。すいませんでした。帰ったら家族サービスに励みますから勘弁してくんねえ。」
午前5時、宿に戻って冷えた身体を暖めようとシャワーを浴びたら、そこの装置がぼろくて冷水しか出なかったのでたちまち凍え、素っ裸でベッドに飛び込みぶるぶる震えた。これは作戦ではなく、多分本当に罰が当たったのだろう。
終わり(2013.4.7)
(※また余談だが、帰り便のチェックインの時、カウンターのアメリカ人からオーロラは見れたか聞かれたので、二晩も見れたと答えたら、彼女は私はオーロラを見ていないという。だって夜は寝ているから、だって。現地人には何の変哲もないありふれた自然現象らしい。それでもねえ、やっぱ日本人にとっては珍しいよねえ。)